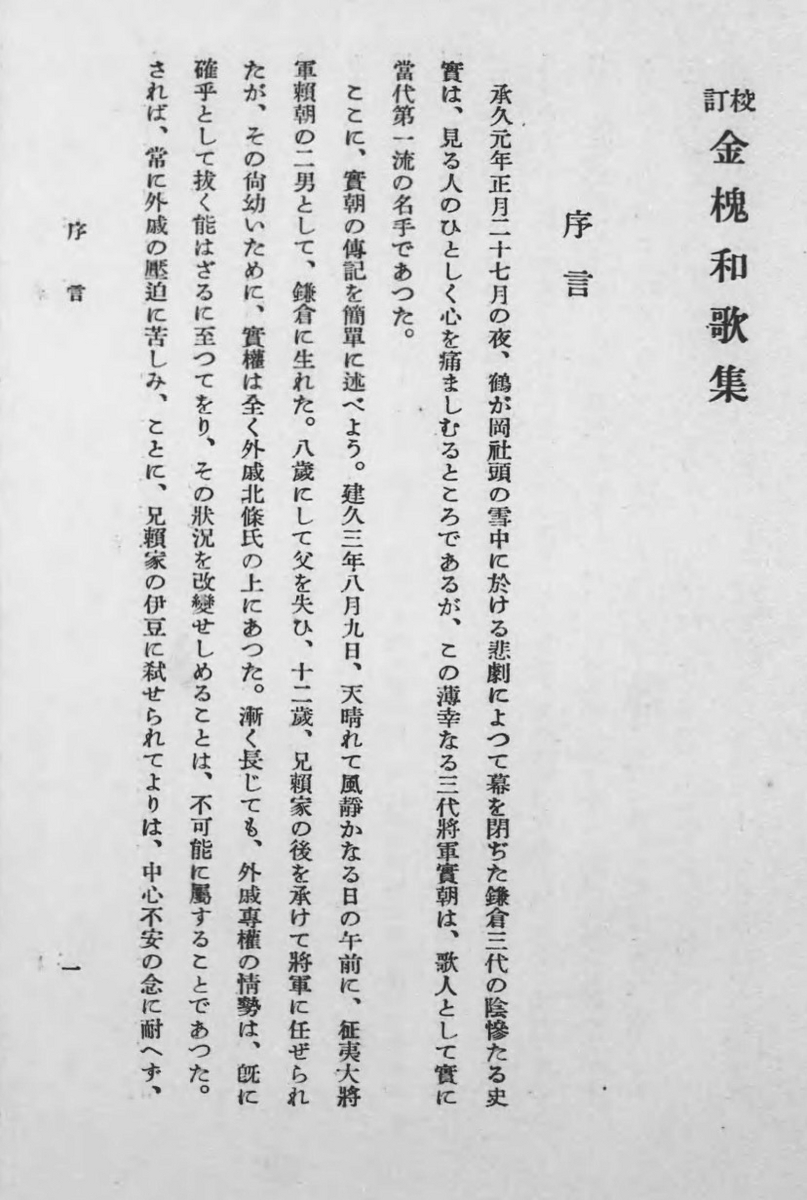林勇『少年 右大臣源実朝』(大同館書店、昭和6年)挿絵(国立国会図書館デジタルコレクションより)
前編のつづきです
※2023年5月25日に 16)官位について の項目を追加しました
3.ドラマと史料類との異動・考察
1) 時政との関係
・ドラマ
鎌倉殿就任後最初のうちは時政が実権を握っていましたが、次第に専横を深め、下文に内容を伏せて花押を書かせて、時政夫妻にとって目障りな畠山重忠を討ったりしました。それに危機感を持った義時、政子の動きに対抗するために、牧の方にも扇動されて、実朝を廃し娘婿の平賀朝雅を擁立することを画策。実朝を自邸に呼んで監禁し、出家して朝雅に鎌倉殿を譲る文書を書かせようとしますが、拒否されます。抜刀して脅すも、和田義盛がやってきて押しとどめ、実朝の慰め手になります。そうこうするうちに義時が軍勢を集めて時政邸を囲み、実朝引き渡しを要求。実朝は解放され、時政は出家して伊豆に引退します。
・史料・研究との比較
ドラマでもあったように、実朝政権初期は時政が主導しています。千幡は時政の名越亭で元服し、翌日将軍家の政所始が執りおこなわれ、別当の時政が吉書を実朝の御前に持参しました。またこの日、実朝は初めて甲冑を身につけ、馬に乗り、それらの儀式は時政が中心となって実朝の介添えをしました。
その頃の幕府の発給文書が、将軍実朝の命令を奉じたというかたちをとりつつ、奥下に時政ひとりが署判する下知状形式の文書が中心であったことからも時政主導がわかります。(五味 2018)。
ただ、重忠追討のために時政が嘘をついて実朝に下文に花押を書かせた…ということは史料にありません。また実朝排除の動きはしたようですが、拉致して出家と鎌倉殿の譲位を迫ったという記録もありませんし、義盛がそこに乗り込んだ記録もありません。
牧氏事件については、牧の方が時政邸にいる実朝を廃して平賀朝雅を将軍に擁立しようとしているとの「風聞」が立ったために、政子は即座に長沼宗政、結城朝光、三浦義村・胤義、天野政景らを派遣して実朝の身柄を義時邸に移した、ということが吾妻鏡に記されています。その風聞が真実かどうか、具体的に「廃する」(原文読み下し文は「当将軍家を謀り奉る」)とはどのようなことなのかは不明です。ただし『愚管抄』では牧の方が「関東ニテ又実朝ヲウチコロシテ、コノ友正(朝雅)ヲ大将軍ニセント」と動いたと記しているので、実朝殺害計画があった噂があったことがわかります。
・考察
時政主体の政治であったこと、牧氏事件の大枠の流れはドラマは史実に基づいています。ただ細部は色々異なります。
重忠追討の下文、及び出家する旨の起請文の下りは完全に創作ですが、それを通して「書類に将軍が署名する重要性」を少年実朝が自覚していく過程を印象的に描いていたと思います。重忠の件で勧められるままに署名することの恐ろしさを知った実朝は、出家と譲位の文書に頑として署名しません。
またこのエピソードは「親族だから信じる」という気持ちを持つことの危うさも実朝に悟らせる機会になりました。もっともまだまだ信じたい気持ちが残っているのは、そういう仕打ちをされてもなお時政にそばにいてほしいと思ったり、出家の件も自分の意志もあるが政子や義時に相談してからという言い方になってることからもわかります。
ドラマでは牧氏事件の大枠は描写しつつ、細部を創作したり変更したりていくことにより、実朝の成長段階をたくみに描写していったと言えましょう。
なお、なかなかイエスを言わない実朝に、時政が抜き身の剣を持って立ちはだかる、という描写は、『愚管抄』の殺害計画があった記述を反映しているのかもしれません。
2) 疱瘡
・ドラマ
「穏やかな一日」は1208〜11年を一日に圧縮して伝えるという特殊な回ですが、そこで実朝が疱瘡にかかったことが最初に示されます。彼が疱瘡の跡を結構気にするシーンが入っており、起き出して鏡を見ながら跡を触ったり、政務につきなながらもつい触ってしまって、医者から触らない!と言われたり。義盛からは、跡がありますねえとデリカシーゼロで言われますが、でもあったほうがサマになりますよと言われて思わず笑ってしまいます。
政治的には、その間政子が実朝の代行をしたことが語られ、実朝は母上に迷惑をかけたと言って、これからは自分が頑張らねばということを言います。
・史料・研究との比較
承元二年(1208年)2月、実朝が疱瘡にかかったため鶴岡八幡宮で神楽が催されたという記事が吾妻鏡にあります。大江広元が神拝を行い、御台所も参宮しましたがなかなか癒えず鎌倉に近国の御家人が詰めかけたのですが、19日に平癒しました。
しかし疱瘡の跡が残ったために、それを憚って1211年2月21日までの3年間、鶴岡八幡宮に参拝していませんでした。その間は、二所詣(頼朝が始めたもので、将軍が御家人を引き連れて箱根権現、伊豆山権現、三嶋大社に詣でて幕府の安泰を祈願する)も行われず、将軍が幕府祭祀に参加しないという特殊な事情が生まれていました(山本みなみ 2022)
・考察
疱瘡の跡について気にする描写は、鶴岡八幡宮や二所詣という、将軍として重要な祭祀を行えないほど疱瘡の跡を憚っていたという史実を拾い上げた描写だったと思います。参拝に絡めなかったのは煩雑さを防ぐためでしょうか。疱瘡の跡はドラマでは最後まで残る演出になっています。
三年間将軍として大事な祭祀に関われなかったこと、それを政子が補っていたことは、疱瘡に罹患していた間のこととしてドラマ内で描かれました。そしてそれにより、母に頼らず為政者として奮起しようというきっかけになっている描写は、実朝の成長段階を示す上で効果的な筋書きになっていたと思います。ただ、政子が頼朝の後家として大きな権力を持っていたらしいことまでは描写されておらず、たどたどしく幕府の機構を述べたり、学んで損しちゃった、と言ったりと、かなり拙い感じに描かれてたのが気になりました。
3) 和歌への傾倒
・ドラマ
政子の口から、実朝について雨垂れを一晩中眺めるような感受性の鋭い少年であることが語られ、「政よりよほどまし」ということで、和歌を学ばせてやりたいと述べます。それを受けて三善康信が和歌の手ほどきを始めますが、和歌を為政者の欠かせぬ勤めと知ってその方向でやらせたい実衣が、京から来た源仲章を師匠として連れてやってきて、康信を追い出します。康信が「花鳥風月を感じるままに」詠むようにすすめるのに対して、仲章はそれは忘れるように言い、代々のみかどが望む国の姿を詠み継いできたものを知らなければ学んだことにならないとし、和歌に長ずるものが国を動かすとも言います。(1204年時点)
後に政子は、頼朝が遺した書物から自ら実朝が好みそうな和歌を書き写して、実朝の目に触れるところにそっと置かせました。実朝はそれを目にして和歌の素晴らしさに改めて目覚め、政子に伝えに行きます。そこで一番気に入った歌「道すがら 富士のけぶりも わかざりき 晴るる間もなき 空のけしきに」が父の歌であると知り、大変嬉しく思います。(結婚の前くらい)
その後も基本的には仲章から指導されつつ、不在の折には康信からも指導されて歌道に励みます。「けさ見れば 山もかすみて久方の 天の原より 春はきにけり」を吟じると、言葉の順番を逆にした方がいいなどと言われますが、そこに都から戻ってきた仲章が、藤原定家が添削してくれた実朝の和歌を持ち帰ってきます。同じように康信に言われて順番を逆にした「今ぞさかえむ 鎌倉のさと」という和歌を、定家から元の方がいいと指導されたことが判明、実朝の感覚が優れていることがわかります。
また、「春霞 たつたの山の さくら花 おぼつかなきを 知る人のなさ」という歌に泰時への恋心を託し、それを間違いではと返されると「大海の 磯もとどろに よする波 われてくだけて さけて散るかも」と恋に破れた心を表現しました。また最後には辞世の句のような歌「出でていなば 主なき宿と なりぬとも 軒端の梅よ 春を忘るな」を遺した描写がなされました。
・史料・研究との比較
吾妻鏡には実朝の直接の和歌の師匠の名は確認できません。三善康信や源仲章が和歌を教授したという記述もありません。
五味氏は実朝の最初の師となったのは歌人の源光行(源氏物語の研究者として知られ、河内本と呼ばれる本文を定めた)なのではないかと推測しています。元久元年(1204年)に『蒙求和歌』『百詠和歌』を著していますが、いずれも和歌を付した書物で、幼い子供を諭すために著したとあります。ほかにも「幼稚の児童」に教えるために『楽府和歌』をしるしており、幼い実朝が将軍となった直後であるという点からみて、それらの幼い子供とは具体的には実朝を指しているのではないか、それは政子の指示で作られたのではないかとしています(五味、2015)。指導したなどの記述は見られませんが、著書が影響を与えたことは考えられるでしょう。
実朝が初めて和歌を詠んだのは翌年元久2年(1205年)で、4月12日に12首の和歌を詠んだと吾妻鏡にあります。その4ヶ月ほど前に結婚しているので、御台所を通じた京の情報の影響もあるかもしれません。そしてその年の9月2日、藤原定家の門人の内藤朝親が実朝の元に、3月に編集が終わったばかりの『新古今和歌集』を持参しました。頼朝の歌が新古今に撰入したことを知って実朝がぜひ閲覧したいと考え、自身も撰入している内藤朝親に指示して筆写させていたものです。実朝の歌には新古今和歌集の影響が非常に強いとも指摘されており、実朝が新古今和歌集を読み込んで独自に勉強したことを伺わせます。
吾妻鏡では建永元年(1206年4月27日以降)に初めて和歌を学んだという記述があり、初めて和歌を詠み新古今和歌集を入手した翌年が正式な学びはじめの年とされています(「去ぬる建永元年御初学」)。
そしてドラマでも描かれたように、藤原定家とも交流していました。上記の初学に触れた承元三年(1209年)7月5日の条に、夢想のお告げによって二十首の詠歌を住吉社に奉納することにした実朝が、そのついでに定家の添削を受けるため、定家の門弟である内藤知親を使者として、和歌三十首を自撰して送ったというのです。定家はすぐに応じ、全ての和歌に合点を加えて添削しただけでなく、「詠歌口伝一巻」を著して献上しました。知親が帰参したのは8月13日ですから、かなり早い対応ですね。定家との交流はその後も続き、実朝の求めに応じて『相伝の私本万葉集一部』を献上(1212年)するなどしています。
他にも、承元二年には御台所の侍で鎌倉に下向してきた藤原清綱から『古今和歌集一部』を献上されたり、承元四年には大江広元から『三代集』(『古今』『後撰和歌集』『拾遺和歌集』)の献上を受けたりと、和歌に関する書籍を色々手元に集めるようになり、様々なルートでも学びも深めていったようです。
そうして和田合戦後の建暦三年(1213年)末ごろ、実朝22歳の時、それまでうたい溜めてきた歌をもとに『金槐和歌集』が作成されました。
また実朝は和歌を通じて御家人と親しく交流したり、近しい御家人を集めてよく和歌会を開き、和歌の研鑽につとめたりしました。その折りによく好まれた題材が梅でした。
また政治的な場でも和歌を詠み、和田合戦の折に歌2首を添えて奉納したことが吾妻鏡にあります。金槐和歌集でも為政者としての立場を意識した歌や、上皇に向けたと思われる、かの有名な「山は裂け…」の歌が入っています。
なお、有名な辞世の句的な和歌「出でていなば…」は吾妻鏡にのみ採取されていますが、実朝最期の状況に合いすぎていることなどから偽作の可能性が多く指摘されています。実朝の梅好きはよく知られており、京都北野天満宮の梅の種をとってできた梅の木を御所に移して愛でたという記録もあることからも、条件が揃いすぎているという指摘もあります(三木麻子、2012)。大谷雅子氏は『六代勝事記』が創作したものを『吾妻鏡』が踏襲したのではないかとしています。
坂井氏は、現代では文化としか捉えられていない学問や音楽や和歌も当時の政には欠かせないものであり、政そのものだったと指摘します。順徳天皇が記した『禁秘抄』には、天皇には三つの芸能が求められるとし。第一は学問、第二は音楽、第三は和歌であるとしました。和歌は声に出して詠むことによって神仏と交歓し、世を治め、民をやわらげるものでした(坂井 2022)。
・考察
このドラマで非常に画期的だと思うのが、実朝の和歌好きを、従来の多くの見方である「現実逃避」と全く見做さない点です。和歌を単なる趣味のものとして扱わず、和歌が為政者のたしなみであることが仲章や阿波局の言葉から語られ、和歌が政治のツールとして非常に重要であることが表明されたのは大変進歩であると思います。
実権を思うように行使できず趣味的なものに打ち込むという描写は、ドラマではむしろ頼家の描写に少しありました。蹴鞠が政のツールであることは示されましたが、頼家にとって逃避的な意味合いも同時に示されていました。
また従来、実朝の和歌好きは京志向と関連させられることが多かったのですが、ドラマでは京志向と関係なく、詩人としての感性が天性のものであることを強調しています。
ですがその一方で、政治ツールとしての和歌の位置づけが具体的に描写されることはなく、もう少し踏み込んだ描写があればなおよかったなと思いました。ドラマではあくまでも和歌は実朝の個人的な心情の吐露としての側面が重視され、政治的な側面よりもいいものという価値判断がなされています。ドラマ内で印象的に採用された歌が、「穏やかな一日」「八幡宮の階段」いずれも実朝の恋情の歌や辞世の句であり、後鳥羽上皇に向けたと思われる「山は裂け〜」などがなかったことからも伺えます。為政者としての歌もドラマに実は出てきているのですが、下の句のみです。
「宮柱 ふとしきたてて よろづ代に 今ぞさかえむ 鎌倉のさと」
八幡宮の荘厳な社殿の様子を寿ぎ、治世の永遠を祈願する為政者としての実朝の意識がわかるとされるこの歌(三木麻子『源実朝 日本歌人選051』) 、ドラマでは後半しか出てきません。しかし前半に出てくる「宮柱ふとしき立てて」という表現は古事記や万葉集などでお馴染みの表現で、上代的なものです。「太柱をどっかりと立てて宮を造営するという古代的な感覚をよく伝える言葉であり、鎌倉の繁栄を宣言する王者としての実朝の意志を読み取ることができる表現」と三木氏は述べています。ドラマ内でこの歌の全体をしてしていたなら、実朝の万葉調の特色を示すものとしても適切だったでしょう。
なお、実朝がはじめ心理重視型の康信から学び、次に知識重視型の仲章から学ぶのは、史料から伺える独学→本格的に学ぶ という二段階を踏んでいそうな様子、また実朝の和歌の中に独自の感情の発露の和歌と、技巧を新古今和歌集などから学んだらしき和歌が混在していることと合致してるなあとも思いました。
ちなみに雨垂れの件は、永井路子『北条政子』にも出てきており、それへのオマージュかもしれません。そして実朝が音の感覚に優れていたらしきことは、様々な人が指摘しています。
また政子が様々な和歌を書き写して実朝の教材とするというのも、政子が指示して実朝に初学者向きの和歌関係の本を作らせたのではないかという五味氏の推測にマッチしているなとも。そしてその中に頼朝の歌があってそれを実朝が一番気に入ったというのも、実際その歌が新古今和歌集に載ったこと、そのことで実朝が新古今に興味を持ち書き写させて取り寄せたという吾妻鏡の逸話をしっかり踏まえて取り込んでいるなあと感心しました。
4) 結婚と子供
・ドラマ
結婚前から結婚に乗り気でなく、牧の方や実衣がどんどんお膳立てをして坊門家から後鳥羽上皇の従姉妹の姫を御台所に迎えます。結婚後も御台所を避けていましたが、ある日ついに自分が異性に性的に興味を持てないことを告白します。それ以降は仲睦まじい関係で、宋船計画が進んでいる時は一緒に連れて行きたがったり、最後にはお前と引き合わせてくれた上皇様に感謝したいとまで伝えます。しかし子供ができることはなく終わりました。
・史料・研究との比較
実朝の結婚については、吾妻鏡によれば足利義兼(時政の娘で、義時や政子と同母妹が正室)の息女を御台所にすべきではないかとの審議がありましたが、実朝はこれを許容せず、京都に申し入れたのだと吾妻鏡にあります。ですが「いくら将軍の正室とはいえ、十三歳の実朝が時政をはじめとした宿老の提案を拒絶して、自身の意向を押しとおしたとするのは不自然で、逆に、将軍の正室であるからこそ、権力の中枢にある人びとが積極的に関与し、その選定に神経をとがらせたとみるべきと坂井氏は述べており(坂井、2014)、今は同様の見解を示す研究者が多いです。五味氏によれば、「かつて政子は上洛して頼家や大姫の婚姻問題にかかわった経験から、京都から御台所を迎えるように勧めたのはおそらく政子であったろう」(五味、2015)とし、藤原兼子がかかわっていたものと考えられるとしています。実際姫君は兼子の邸宅から出発しています。坂井氏はまた「時政・牧方は後鳥羽の朝廷とのつながりを意識し、その権威を利用するかたちで権力基盤を強化しようと考えたのではないか。一方、将軍の権威が高まれば、将軍に親権を行使しようとする政子たちも同様に地位を上げることになり、政子・義時らにとっても損な選択ではない。つまり、両陣営にとって義兼の息女よりも京都から御台所を迎えるほうが得策だったのである。」(と、時政夫妻と政子の両方の利害が一致したと見ています。山本みなみ氏は牧の方の尽力を重視しています。
・考察
以前は吾妻鏡の記述のまま、実朝自身が御家人出身の娘を推す周囲の意向を蹴って京都出身の姫を強く望んだように解釈されていましたが、今は周囲の大人たち、時政夫妻や政子らの意向であるという見方が多く、ドラマもそれに従ったといえます。ただドラマでは政子はまだ結婚には早いと見ており、積極的には進めていない描写でした。その「周囲の大人主導」で困惑する実朝を、彼の性的志向に絡めて描写したのは、大変新しい解釈と言えます。
彼の性的志向は史料からはよくわかりません。ただ子供もおらず、彼のような立場としては珍しく側室も持たなかったようです。実朝が同性愛者だったのではないかという論文は存在します。
https://opac.time.u-tokai.ac.jp/webopac/TC10001787
またカミングアウトしてからの仲の良さを示すものとして「2人きりで花を見たかった」と言いながら気晴らしに歩き巫女のところに連れて行った挿話がありますが、これは吾妻鏡にあるふたりで永福寺に花見に行ったという逸話を反映させているのでしょう。
・ドラマ
実朝の武芸の指南役として弓や相撲を教えますが、実朝の浮かない様子を見て、気晴らしに自宅へ誘います。そこで一緒にご飯を食べたり、巴御前とのやりとりを見て癒されたり、近所の歩き巫女のところに連れていったりと、癒しの場を提供します。その親しさから、義盛は周囲からも望まれてると言って上総介の任官を望みます。実朝は一旦受け入れますが、政子に相談すると「義盛は私も好きだけれども、政はそういうこととは違う、もっとおごそかなものだ」と諭されます。
・史料・研究との比較
義盛とは史実でも良好な関係を築いていたようで、ドラマと同じく義盛邸に訪問してる様子が吾妻鏡にも伺えます。建暦二年(1212)6月24日に和田義盛の家に赴いた際に引出物として贈られた『和漢将軍影』十二鋪に大いに喜んでいます。その年の8月18日には藤原朝光と和田義盛の二人に、古物語を聞きたいということで、北面三間所に伺候するように命じました。翌年の正月、実朝は広元、義時、時房に次いで四日目の垸飯(将軍への饗応を通じて御家人の序列を公に示すもの)を義盛に務めさせましたが、義盛にとって垸飯の名誉はこれが初めてでした。
義盛が上総介をのぞむという逸話も実際にあります。義盛の要求の件についての妥当性の評価は研究者によってまちまちです。当時義盛は左衛門尉だったので当時の昇進ルートとしてさほど無茶な要求ではなかった(岩田 2021)、頼朝の定めを破る無謀な望みである(坂井 2022)、等など。 ただ、義盛の要求は、近年は北条氏からも数名の受領就任者が出たことが影響していそうだというのは共通して認識されています。実朝が政子にその件について相談し、間接的に拒否されているのも吾妻鏡にあります。
なお、義盛邸や義盛に紹介された歩き巫女などのところへなど、実朝が急に思い立ってふらりと御所の外に行きたがる様子が描かれましたが、実は吾妻鏡でもそのような行動をしているのが見て取れます。実朝が誰にも知らせずに山内辺りを歴覧したので、人々があわてて追いかけたり、実朝が急に思い立って永福寺に近臣を伴って徒歩で出かけたので、後から牛車を遣わせたなどの逸話が吾妻鏡に残されています。
・考察
実朝と義盛の親密な関係は、史実をとてもよく反映してると言えます。
たとえば古物語を聞くという逸話が、「オンベレブンビンバ」回の、義盛邸で実朝に頼朝の逸話を聴くシーンに反映されているのでしょうし、義盛邸に実朝が赴いて楽しむ話も吾妻鏡にあり、ドラマではそれを膨らませた描写と言えます。
もっとも、吾妻鏡では実朝は他の有力御家人の邸宅にも色々訪問しているのですが、それらの描写はドラマではないために、義盛へのスペシャルな親しさが相対的に史実以上に強調されているのは間違いありません。
そして北条氏のみから受領が出るのはいかがなものかと、ドラマでも八田殿に言わせており、そのあたりの北条のみが将軍外戚としていい思いをしている点の不自然さを史実を踏まえて描写して、義盛の要求にも一定の理があることを示唆しています。
また実朝が、割と思い立ったらすぐに外出したがるという吾妻鏡から伺える性質を、ドラマ上でも描き、鬱屈を晴らすための気晴らしを求めての行動と解釈して表現しており、これもうまい活かし方だなと思いました。
6) 和田合戦
(実朝が関係しない部分は省略しました)
・ドラマ
和田氏が北条氏の強敵となることを恐れた義時は、和田一族が関係した実朝への謀反の件に絡めて和田氏を挑発します。息子たちは赦免されても甥の胤長は許されず、一族の前で面縛の屈辱を受けて流罪にされ、その屋敷も一族に下げ渡されず押収、胤長の幼い娘はショックで死んでしまい、一族の怒りは頂点に。それでも義盛はなんとか実朝への忠義は貫こうとし一族を抑えようとします。
戦を止めたい、義盛に会いたいと強く言う実朝ですが、それを受けた政子の発案で義盛を女装させて御所に呼び、直接顔を合わせて諭します。義盛は義時とも話し合い、一旦収まったかに見えましたが、義盛が実朝に引き止められて双六を打つことになり、この帰宅の遅れが和田一族を刺激してしまいます。
一族の若手の打倒義時の勢いは抑え難く、義盛の帰宅が遅いことを理由に兵が出撃します。それをトウから知らされた義時は、ひとり打っていた碁盤を怒りのあまりぶちまけてしまいます。
広元は頼朝以来の文書記録を八幡宮に移すと言い政所に戻ります。義時は実朝と御台所、政子らを西門から八幡宮へ逃します。和田勢は御所の南門から突入すると義村軍と戦闘状態に。泰時は西門を守り、なんとか撃退します。和田勢は由比ヶ浜まで撤退して兵を整えます。
翌日義時は、曾我・中村・二宮・河村が和田勢に加勢にやってくるので御教書を出して幕府方に着くように言うように実朝に迫ります。渋る実朝に、このままでは鎌倉が火の海になると脅して、なんとか御教書を出させるのでした。
・史料・研究との比較
建暦三年(1213年)5月の和田合戦については『吾妻鏡』と『明月記』に詳しい記述があり、後者を前者の記述の参考にしているのはよく指摘されています。簡潔な記述は『愚管抄』にもありますが、それは吾妻鏡や明月記の流れとかなり異なります。
まず吾妻鏡と明月記の流れを見ていきます。
(1) 合戦まで
胤長の屈辱の件やその娘の件は吾妻鏡にあり、吾妻鏡をかなり踏襲しています。一族の若手がいきりたつのをなんとか義盛が宥めるというのもその記述通りです。
ただ吾妻鏡などでは、実朝が義盛と直接会って話し合ったとはありません。そのかわり、実朝が真意を確かめるべく、出仕をやめていた義盛に二度にわたり使者を派遣し、その聴き取り内容対して再度使者を派遣して挙兵を思いとどまるように伝えます。つまり史実の実朝も、和田一族の反乱の気配を知ってすぐに鎮圧しようとするのではなくなんとか思いとどまらせようと努力しています。
(2)合戦の経緯
⚪︎義村の裏切り
ドラマでは直前に義村から裏切りを聞き取っていますが、史料ではそれを察知していた形跡がありません。実朝や政子らの身柄を押さえて自らの正当性を確保しようとしていた義盛は、義村に御所北門攻撃を担当させて起請文を書かせていたのですが、義村が翻意したためにその北門から実朝らが脱出してしまい、目論みを達成することができませんでした。和田勢は御所南門、義時邸、広元邸の三ヶ所に攻撃を仕掛けます。
⚪︎実朝らの避難
和田軍集結の話を聞き、その時碁会をひらいていた義時、宴会を開いていた広元は急ぎ御所に駆け付けます。
政子と御台所は鶴岡八幡宮の別当坊に避難。明月記では実朝は広元といっしょに御所の北にある頼朝の墓所法華堂に逃れました。『吾妻鏡』では政子と御台所が逃れた後も実朝らは御所に残りますが、和田勢が御所に火を放った後その火災を逃れるため、実朝、義時、広元は頼朝の墓所法華堂に逃れました。
⚪︎戦いの推移
吾妻鏡によればその日一旦由比ヶ浜に引いた和田軍は、翌日南武蔵の横山時兼や波多野盛通らが参戦、味方を得て再び攻勢に転じます。
辰の刻と巳の刻に軍事動員のための御教書が御家人に出されます。兵を出して近くに陣取っていたものの、幕府につくようにとの連絡にも様子見をしていた曾我・中村・二宮・河村の輩たちに再度催促の将軍花押つき御教書をつかわせたところ参戦。次いで義時、広元の連署に将軍の御判付き御教書を武蔵国など近国の御家人に出します。
その後若宮大路で戦っていた泰時は法華堂に遣いを出し、多勢の勢いではあっても敵を破りがたく重ねてどうすべきか考えてほしい、と伝えます。実朝は大いに驚き、防戦の事について評議が行われ、広元が政所から召され、将軍の立願の願書を執筆し、その奥に実朝が自筆で歌二首を加えて鶴岡八幡に奉納しました。
・考察
和田合戦は、吾妻鏡や明月記での描写を全て映像化すると大変煩雑、矛盾したものになるので、基本的な動き、人々の心情は概ね吾妻鏡に添いつつ、時折明月記に添い、全体に適宜改変している印象です。
たとえば吾妻鏡に見える合戦前の二度にわたる使者派遣での義盛真意確認&説得は、義盛が女装して御所に赴き直接実朝や義時と会話することに統合されています。和田勢集結の話を聞いたのは義時が碁会を開いていたという逸話は、義時が義盛を懐かしんでひとり碁を打っているシーンに活かされていました。(義盛の帰宅の遅れから一族が判断を誤り出撃してしまう、というのは吾妻鏡の記述と異なりますが、もしかしたら仁田常忠のエピソードを転用しているのかもしれません。)
また戦が始まると実朝たちが御所から逃れたのですが、吾妻鏡では実朝、義時、広元は法華堂に逃れ、政子たちは鶴岡八幡宮に逃れていますが、ドラマでは政子たちと西門から八幡宮に最初から一緒に逃れたことになっており、逃げた先が変更されています。また逃げるタイミングを放火前に軍集結の話の時点にしたのは明月記に従ったものと思われ、またそちらの方が合理的でもあります。
将軍御教書が戦いの途中で出されたということは吾妻鏡にありますが、ドラマでは実朝が躊躇いかなり揉めた感じに脚色されています。また御教書は2回に分けて別方面に発信されているのですが、近隣に様子見で陣取っていた御家人向けの話だけに絞り、しかも彼らは和田に加勢するためだったと変えていて、御教書発信の必要性&緊急性を印象付けています。実際はどちらに付くか迷っていた状態でした。
また若宮大路で戦う泰時からの苦境の連絡とその対応が表現されていません。これが表現されていれば、おそらく戦勝祈願のために実朝が和歌を奉納するという政治的な和歌の活用シーンが描けたのに…とは思いますが、私の見るところ、尺の都合もさることながら、義盛の最期で実朝と泰時が劇的に再会する時のために、それまでは2人の接触は文書レベルでも避けたのかなと思いました。
7) 義盛の最期と実朝
・ドラマ
義時が和田方との戦闘について、広元が和田勢を追い詰めたと嬉しそうに義時に告げます。すると何か考えた義時は、実朝に戦場に出て投降を呼びかけて欲しいと言います。実朝も義盛を説得できると乗り気になり、実朝は鎧を狩衣の上から身につけた姿で姿を現し、義盛に呼びかけ、お前に罪はない、これからも支えてくれと呼びかけます。息子たちを従えてそれを聴いていた義盛は感極まり、自分は実朝の鎌倉一番の忠臣だと一族に語りかけますが、義村が合図して一斉に矢を射掛け、義盛は全身に矢を受けて絶命。義時はこれが鎌倉殿に取り入ろうする者の末路であると大声で言います。
幕府勢が一気に和田勢に攻めかかる中、義盛を騙し討ちにされた実朝は泣き咽び、泰時に連れられて鶴岡八幡宮に避難するのでした。
・史料・研究との比較
吾妻鏡では、実朝が戦闘の場にいたとはありません。実朝は御所から法華堂に脱出してから終始そこにとどまっています。
また義盛の死についてですが、吾妻鏡によれば酉の刻、義盛の息子の和田義直が伊具馬太郎盛重に討ち取られると、義盛は歎息し、年来鍾愛の義直の所願を頼んでいたのに、今となっては合戦に励んでも無益、と声をあげて悲哭し、東西を駆け回った末、ついに左衛門尉大江能範の所従によって討ち取られたとあります。ドラマのように大勢に矢に射られて死んだ記述はありません。その後息子の義重・義信・秀盛らも討死し、豪傑朝比奈義秀らが蓄電するなどして、幕府方の勝利となりました。
義盛の死後、実朝は何度か供養をしています。たとえば建保三年(1215年)11月、義盛以下の死者が御前に群集した夢を実朝が見たため、翌日急遽仏事が行われました。
・考察
全体におおよそ吾妻鏡(たまに明月記)に添った描写だった和田合戦ですが、この義盛最期に近づいたところからそこから大きく離れ、大変ドラマチックなものになっていきます。
(2)合戦の経緯 でも書きましたが、吾妻鏡によれば合戦翌日は泰時もなかなか破り難いとの連絡を法華堂に送るほどですから、幕府方は義盛や義直の死の前はドラマの広元が言うような楽観的なムードではなかったと思われます。またその日、和田勢に南浦和の御家人が加勢したことがドラマでは割愛されており、実際以上に和田勢が劣勢な印象の作劇と言えます。義盛の死を契機として和田勢が敗れたことはドラマも吾妻鏡も共通していますが、ドラマではそれ以前にすでに勝敗が決していたような感じにしていたのが違いとして挙げられます。実際のところは幕府は「紙一重の勝利」だったと坂井氏は指摘しています(『考証 鎌倉殿をめぐる人びと』)。
実朝が戦場に姿を現して説得するも、その目の前で寵愛していた忠臣義盛が惨殺される…という非常にショッキングで印象的なシーン、吾妻鏡の記述とは全く異なり、完全な創作です。確かに大混戦の戦闘の只中に、大事な鎌倉殿をわざわざ引っ張り出すことは、実衣の言っていたように大変危険なことです。源平合戦のような、御家人をまとめて一丸となって敵と闘うという、武家の棟梁たる資質を示す華々しい戦闘の場ではなく、いわば臣下同士の戦いの色彩が濃い反乱な訳ですから、鎌倉殿の命を危険にさらすことはあまり意味があるとは思えません。それに万が一和田勢に実朝の身柄という錦の御旗を確保されたら一発逆転されてしまいます。
またドラマ上でも史実でも、和田勢が御所に攻め込んだというだけでなく、火を放って全焼させてるので(御所に火の手が上がった、燃え尽きてしまうのだろうかとは実衣の言葉で表されていますし、燃えている遠景も映っています)、義盛に大変同情的だったとは言え、罪はないとまで皆の前で断言するのもちょっと不思議な発言と言えます。
そのあたりの整合性よりも、舞台のようなシチュエーションや極端な言葉によって、実朝の未熟さと因果応報的な展開を視聴者に見せつけ、実朝に不満を持つ義時との対立構造を印象づけたいという制作側の意図を感じました。ドラマ上では勝ちが決まりかけていた段階で敢えて実朝を戦場に引っ張り出して義盛と対峙させた義時像にも、実朝の未熟さを知りながらそれを白日の元に晒してやろうとするような悪意を感じてしまいます。万が一にもちゃんとした対応をしてくれればそれはそれでオッケー、予想通り贔屓の引き倒しのような対応をするのであれば、それを口実に義盛を討ち、北条以外の御家人を贔屓にしようとする実朝に打撃を与えられると踏んでいるようです。そして後者の展開になりました。
で、そのドラマチックな展開に対してヒントを与えたのではないかと私的に思っているのが、『愚管抄』の記述です。愚管抄では
「義時ガ家ニ押寄テケレバ、実朝一所ニテ有ケレバ、実朝面ニフタガリテタゝカハセケレバ、当時アル程ノ武士ハミナ義時ガ方ニテ、二日戦ヒテ、義盛ガ頸トリテケリ」
と、なんと実朝は義時邸にあり、義時は実朝を正面に立てて戦ったというのです(五味 2015)。最初から最後まで実朝は戦場にいなかったとする吾妻鏡&明月記とは真っ向から対立する記述です。最後に実朝が陣頭に立つというシーンは、ここからきたのかもかと思いました。(なお、愚管抄の作者慈円は、実朝が武を怠ったという非難を一貫してしてる人物であるにも関わらず、そのように実朝が陣頭に立ったことを書き記してるので、慈円の主観でなく当時ある程度流布していた話ではないかという意見もあります(藪本 2022))
そのように、合戦の当初の推移よりもかなり吾妻鏡などの記述からは離れ、ドラマとしてやや強引な描写になってしまいましたが、実朝(泰時も)の受けたショックの測り知れなさを劇的に表現することで、和田合戦以降の実朝の積極的な将軍権威拡大政策の理由づけ、道筋をつけるものとしては、物語上大変有効な作劇だと感じました。
8) 政治への取り組み姿勢
・ドラマ
最初は時政からじいにおまかせください、と言われ、その通りにしていたら畠山討伐の下文によく読まずに花押を書いてしまうなどの失敗をします。
「穏やかな一日」では、疱瘡からの回復後、心機一転頑張って政に取り組もうとします。しかし高野山の所領についての訴えについて、自分なりに意見を述べようとするも義時ににべもなく遮られて発言させてもらえません。自分はいてもいなくても同じなのではないかと悩みますが、泰時から励まされます。
しかし和田合戦の衝撃を契機に、やはり御家人に任せず自分の政をしようと決意し、自分でなんでも裁断するという後鳥羽上皇を手本にしようとします。
泰時を側近に据え、三善康信の協力も得て自分の政を推し進める体制づくりへ。しかし、日照り続きなので年貢を減免しようと、たとえば将軍御領だけでもという案を出すも、実施してみると他の領地の領民から不満が出てしまい、義時がお前たちがしっかりしないからだと実朝の近臣を恫喝します。
しかしそれにもめげず、泰時に上皇から贈られた聖徳太子の肖像を見せて、自ら徳を高めて良い君主にならねばならないと言います。
その流れで陳和卿の話からヒントを得て船を創って宋へ渡航させ、仏舎利を得てこようと計画します。自分もいずれ宋にわたってみたい、共に来てほしいと、泰時と御台所に言います。しかし陳和卿の話は上皇からの差金で、実朝の権威を高めようとするものだと知った義時は設計図を書き換えさせて進水に失敗させます。
またそれにもめげずに政子からの知恵で京から後継者を迎えて大御所になる構想を持ち、自らの地位を高ていく実朝。実朝の政治への意欲は最後まであり続けました。
・史料・研究との比較
坂井氏も五味氏も、実朝18歳の承元三年(1209年)から親裁を始めたという認識で一致しています。
五味氏は実朝が承元三年四月に従三位となり、公卿として政所を開設する資格を得たことに注目し、親裁権を行使しはじめたとします。発給文書も鎌倉殿下文から「別当」が四名から五名、「令」一名、「知家事」一名の各家司が署判する将軍家政所下文に変わり、政務の中心機関である政所を基盤にした親裁の形式も整いました。
坂井氏は実朝の親裁ぶりに注目します。1208年の時点では、御家人の恩賞に関する訴えが義時に進上され広元が実朝に取り次いだという記述がありますが、承元三年の高野山大塔料所備後国大田庄の年貢対捍問題をめぐる訴訟においては、そのような記述はなく、実朝が直に裁断した様子があります。その訴訟の場で、高野山の寺家の使者と地頭三善康信の代官が、「御前の近々」にもかかわらず口論におよび、ともに追い立てられたというのです。実朝は、しばらく訴訟の審理を中断するようみずから直接に命じました。審理が「御前の近々」であったこと、実朝が「直に」命令を下したことは、実朝の意思によって裁定が下される将軍親裁がおこなわれたことを意味していると坂井氏は述べます。それ以降、実朝が「直に」裁断した記事が増えていきます。
坂井氏は以下のように述べます。「以上の事例から読み取れるのは、実朝が御家人たちの主君「鎌倉殿」として、また武家政権の首長「将軍」として、強い自覚と意志をもって訴訟に臨み、御家人たちに接していることである。三善康信や三浦義村のような頼朝期以来の有力御家人が訴訟当事者であっても、いっさい怯むことなく自身の信じるところにしたがって裁許を下している。」
「しかも、そこにはある種の「公平性」が認められる。問注所の調査を受けておこなった審議では荘園領主側の主張を退け、現地の牧士と奉行との喧嘩事件では権力を濫用した奉行の御家人を更迭し、御前での弁論の激しさが度を越せば荘園領主側・御家人側双方に審理の中断を命じている。こうした「公平性」は主君にとって、また統治者にとって不可欠の資質であろう。 一方、実朝が「鎌倉殿」「将軍」として下した命令を拒否、もしくはなおざりにした御家人にたいしては、みずから譴責を加えて謹慎させるという断乎たる姿勢もみせる。ただ、それも頑なで機械的なものではなく、土屋宗遠を宥免した事例にみられるように柔軟性をもちあわせてもいた。御家人たちにたいするこうした姿勢の背景には、頼朝時代の先例や頼朝の命日を判断の根拠にもちだした点からもわかるように、敬愛する亡き父頼朝を範とする思いがあったと考える。伝統文化の吸収にあたって後鳥羽を範とした実朝は、将軍親裁を遂行するにあたっては頼朝を範としたのである。」(坂井 2014)
また2019年に田辺旬氏が明らかにしたことですが、政子の仮名奉書がいくつか実朝将軍期から発給されており、いずれも御家人の所領支配や相続に関わることで、東大寺や京都有力寺社などの幕府以外の権門あてあることが判明しています。よって、政子も実朝と共に政権の重要な決定権を持っていたことが伺えます(『源実朝 虚実を超えて』)
「和田合戦後の建暦三年後半以降は、義時・広元も実朝に協力して幕政を安定させてきた」というのが坂井氏の見立てであります(坂井 2014)
また五味氏は政所発給の下文に着目して、実朝の時代を三期に分ける見方を示していますが、その中で第三期にあたる1216〜1219年に最も将軍権力が増大したとしています(『吾妻鏡の方法』151〜154ページ) 。つまり10代で既に親裁を開始し、1216年からは更に将軍権力が強化されたという見方です。
いずれにしろ、和田合戦以降に無気力になったということは現在の研究成果では否定的になっています。
・考察
従来型の実朝像は、特に文芸作品においては、最初はいい判断をしたりするものの和田合戦の後に政治に興味を持たなくなったり、厭世的になったと言う『右大臣実朝』のような見方をするものが多いものでした。学習漫画などでは、最初から北条氏に実権を握られて和歌などの京文化に耽溺したり無気力になったりする人物として描かれる傾向にありました。
しかしドラマでは、和田合戦以前から政に自分なりの意見を持って取り組もうとしていました。義時にその意志をへし折られそうになりながらも頑張り続け、和田合戦以降に、自分の政を行うために権力を高めなければならないという意識を改めて強く持ち、次々と施策を打ったり身辺を泰時などの味方で固めたりする様子が描かれました。悲しげ、苦しげな時はあっても、一貫して為政者として無気力であったことはなく、まさに「新しい実朝像」と言えるでしょう。そして和田合戦以降ますます将軍権力を強化しようとする動きであること。これらは最近の研究成果とも整合性のある実朝像です。
最近の研究成果との整合性といえば、政子とのタッグでもを感じました。上で述べたように、政子が源氏の家長として鎌倉幕府管轄以外の権門に対応していた可能性、次期将軍交渉役になったのもその延長線上にあるかもしれないとの指摘がある通り、政子が対朝廷に対して従来よりも太いパイプを持っていた可能性が考えられます。そのような近年の研究動向をふまえると、政子からの提案を受けて実朝が京から後継者を迎える話をする、という展開もあながち荒唐無稽ではありません。また実朝の下文に連ねて政子の名前を付す形式は、実朝の権威を政子の権威で補助しているようにも見えます。坂井氏は親王将軍という発想が政子や義時から出たのではという見方があるが、二人の地位からしてありえない、としています。親王をという発想は確かに実朝由来かもしれないですが、京から後継者を迎えようという発想を持ったのは上記のような政子の活動からも自然だったと言えそうです。
ただし、政治への意欲、取り組みはそのように研究成果を反映させてると言えるものの、実朝が主体性を発揮させる時期は後ろにずらされています。和田合戦という強烈な事件で、父とも兄とも慕う義盛を惨殺されることを契機として政に目覚める、とした方が確かにわかりやすい、というのと、義時との確執を全面に出したいという思惑の両方が合わさって、そのようにしたのでしょう。
そのため、実朝が有力御家人に関わる案件でも毅然として突っぱねるという逸話が、和田合戦以前に起きてるために実朝が義時にやり込められる逸話に変えられてしまっていました。
9) 政治内容について
・ドラマ
和田合戦以降なんとか善政をしようとするもなかなかうまくいかない様子が描かれます。日照りの際に、まずは将軍家領に限って減税を試みようとしますが、他の御家人の民から不満が出てしまい、義時に近臣が一喝されます。また自分自身の徳を高めようと宋に船を送って仏舎利を得ようとしますが、義時らの反対にあう上に進水失敗します。
一方で政子の助言に従って大御所になる構想を立てました。政子はそれにより「あなたが鎌倉の揺るぎないあるじとなる」と言い、実朝自身も「父上も見なかった景色を見る」と言っているので、引退するということではなく、天皇と上皇のようないわば院政をしく構想であることが示唆されています。
・史料、研究との比較
吾妻鏡では基本的に善政をしいた政治家として描かれています。特に和田合戦あたりまでは、頼朝の正統派な継承者として描き出されているとの指摘もあります(藪本 2022)
記述の少ないと言われる時期も、雨乞いなどで実績をあげており、寺社の建立や参詣などにも熱心です。以前はそういった宗教関係の事績は政治的な行為と見做されず、現実逃避的にすら受け止めてられていました。しかし最近では、当時は祭祀行為も重要な政であり、「古代・中世の社会では、神社・仏寺の経営が順調になるよう策を施し、神仏の威光を輝かすことは国土安泰・五穀豊穣を実現するに等しく、統治者の責務であった」(坂井 2014)ことがわかってきました。
そして減税免税などの施策は明らかに良い施策として描かれており、それに対する批判的な記述はありません。
課税関係の記事はいくつかあります。
まず将軍就任後、建仁三年(1203年)11月19日に、関東御分国と相模・伊豆両国の百姓に今年の年貢を「将軍御代始」ということから減額し、「民戸を休めらるるの善政」を実施しています。その翌年、駿河以下三ケ国の内検(仮調査)を実施する予定だっのを、撫民のため四月十六日に延期と決めています。この辺りはまだ政子の計らいによる善政と思われます(五味 2015)。
1205年3月には諸庄園の年貢についてきちんと納めるように宗掃部允孝尚を奉行として命じています。
1211年12月27日には来春に駿河・武蔵・越後の将軍家知行国の大田文を整えるように政所の行光、清定に命じています。大田文は課役賦課の原簿となるものでした。
和田合戦のあった建暦三年(1213年)、西国にある幕府の関東御領に朝廷が賦課してきたのですが、広元らは臨時税をすべて拒否するよう進言ました。これにたいし実朝は、まったく収めさせないわけにはいかないが、突然の課税では現地の雑掌も負担しがたいであろうから、今後については前もっておおよその課税額を決めてから命じてほしいと朝廷に返答するよう指示。御家人の都合を勘案した案を朝廷に提示するよう指示しています。
建保二年(1214年)の五月中旬から六月にかけて旱魃が続いて諸国の民が嘆き愁えたので、実朝は6月3日、栄西の言に従って祈雨のために八戒を守り法華経を転読し、義時らも般若心経を読むなどしました。すると二日後に雨が降り、実朝の懇ろな祈りが通じたと思われたといいます。またさらに実朝は、6月13日、鎌倉殿直轄の荘園である関東御領の年貢三分の二を、この秋より毎年一ヵ所ずつ順に免除するという徳政を実施しました。
また実朝は交通インフラ関係にも尽力しています。御台所の女房が盗賊にあったことをきっかけに「駿河国以西の海道の駅家等の結番・夜行番衆、殊に旅人の警固を致すべし」と命じ、駿河以西の東海道の安全確保をはかりました。その1年後に、その命令が充分実施されていないことを受けて実行するよう再度きびしく指示。また、頼朝がその帰り道に落馬したので修理すべきでないという議論が起きた相模川の橋について、二所詣や庶民の往来の妨げになるとして修理を命じた有名な逸話もあります。
課税・減税やインフラ整備といった、現代人にもわかる施策もしっかり行い、かつ中世人ならではの祭祀的な政もちゃんとしていたというのが全体的な実朝の政治活動の印象です。
もっとも治世の最後の方には民の負担になるようなことを計画して諌められたり(京から高僧を呼ぶなど)、あるいは実際に都人への贈り物などで民に負担がかかったことなどのマイナス点が述べられますが(それに対比するように義時の徳のある行動も述べられます)、それらは実朝暗殺事件という「幕政史上稀に見る不祥事」を正当化・必然化し、かつ源氏から北条氏得宗家への権力移行が必然であったという理由づけをするために意図的に悪く描かれたものだという指摘があります(藪本 2022)。
・考察
実朝の政については、残念ながらドラマでは全面的にかなり否定的で未熟さの表れのようになっていて、肯定的に描かれがちな史料との違いが明白になっています。
ドラマではおそらく吾妻鏡にある1214年の関東御領の減税の件を、吾妻鏡にはない批判的な文脈に改変して参照したと思われます。減税を良い政治ととらえず、対象ではない民衆が文句を言うからダメだとし、対案として他の場所にも減税を広げて減税率を変えるなどの考えを出さない考え方は、かなり今日の日本で見られる考え方で興味深いところです。
吾妻鏡では雨乞いなどで実朝の超自然的なパワーが描かれていたりもしますが、それも全く触れられていません。将軍の勤めである二所詣や、民の利便、臣下の往来などを考えて様々な交通整備などの施策がなされた様子も全く描写されておらず、義時に阻まれて以降は、宋船と後継問題くらいしか実朝の政治に触れられていないので、為政者として撫民をする実朝像が描かれない状態です。
近年は実朝の政治家としての力量が評価される傾向にある中で、ドラマでは熱意はあるが力量がない政治家として描かれてしまっており、そこは大変残念でした。
10) 宋船と実朝
・ドラマ
聖徳太子の肖像を一緒に見ている実朝と泰時のところへ、都から帰ってきた源仲章が陳和卿を伴ってやってきます。陳和卿は実朝を見て突然涙を流し、前世では医王山の長老、自分はその門弟であったと語ります。実朝は驚き、自分が以前その光景を夢で見たといい、つけていた夢日記を人々に見せます。陳和卿は誰も見たことのないような大きな船を作って宋と交易しましょうと言い、実朝も同意します。
船の建造に関して、実朝は聖徳太子に倣って宋に使者を送ろうとしていると義時らに伝える泰時。余計なことをと言う義時に対し、それは将軍の権威が高まることなので北条には厄介だろうと義村は皮肉を言います。義時は御家人の負担の大きさを気にしてるのだと言います。そこへ泰時が、夢日記を盗み見た仲章が仕組んだものではないかと言い、上皇の差金だと義時らが気づきます。
義時や時房が御家人の負担を理由に中止を勧めますが、実朝の思いのこもったものだと三善殿が擁護。もう造船をやめると投げやりになる実朝に、泰時が船に御家人の名前を記して鎌倉殿と御家人の絆の証にしたらと提案します。
政子は迷いながらも実朝を後押し。そうこうするうちに造船計画を阻止しようと義時は設計図を密かに書き換えさせます。船の進水式の日、案の定重みが多すぎて船は進水させられず、由比ヶ浜で虚しく朽ちていくのでした。
・史料・研究との比較
吾妻鏡の描写を見ますと、建保四年(1216年)実朝に拝謁した陳和卿が、実朝は前世では医王山の長老、自分はその門弟であったと涙ながらに語りました。実朝は、今まで誰にも話したことはなかったが、建暦元年(1211年)6月3日、同じ内容の夢想の告げを得たと応じます。実朝は前世に住んでいたという「医王山」、中国の育王山阿育王寺を参拝したいと思い立ち、宋人の技術者でもある陳和卿に、中国式の構造の巨大な唐船を建造するよう指示。さらに、結城朝光を奉行に任じ、付きしたがう人員「六十余輩」を定めました。義時と広元がしきりに諫めましたが実朝は聞き入れることなく造船の決定を下しました。ちなみにそれが源仲章を通じた上皇の差金というのは史料にありません。
ちなみに実朝の聖徳太子信仰については、早くから吾妻鏡に記述があります。1210年10月15日には「聖徳太子十七箇条憲法、幷守屋逆臣跡収公田員数在所」などに関する記録を進覧させ、同年11月22日には持仏堂で「聖徳太子御影」を供養したという記事があります。なので1216年に太子像を見ているという描写は整合性があります。もっともドラマの描写ですと上皇からの影響のように見えてしまうとも言えますが。
鎌倉殿自ら宋に渡るという話についての評価は様々です。坂井氏の考察では、それまでも和田合戦の予知夢を見るなどの神秘的なパワーを見せており、その流れで自らの超自然的なカリスマ性を高めるための意図的なパフォーマンスではないかと見ています。(坂井 2014)
五味氏は吾妻鏡の記述を割とそのまま受け止めています。五味氏は、実朝渡航計画はかなり真剣に考えていて、そのための準備をしていたと見ています。実朝は自分がいなくとも幕府はやっていけると考えていたとしており、12月1日には諸人の愁訴が積もっていることを聞くと、年内にその裁判を行うように奉行人らに指示を与えているが、それは国内の政治に目鼻をつけ、大陸に向かおうと思っていた証拠ではないかとしています(五味 2015)。(筆者的には、確かにその年の12月まではそういう記述があるものの、翌年〜船完成まではぱったりそういう記述が見当たらないので、それは留保すべきかなと思います)
吾妻鏡では出帆に失敗しそのままになったという記述で一般にそのように考えられていますが、異伝もあります。『吾妻鏡』成立時期と似た時期に無住が編んだ『雑談集』(1305年) 、第6巻「錫杖事」に、実朝修造の「唐船」による入宋使節派遣の記述があります。それによれば船は葛山景倫を中心とする渡宋使節を載せて由比ヶ浜から出港し、筑紫に差し掛かったところで実朝暗殺の知らせを受けて中止しました。同様の記事が他にもあります。『紀州由良鷲峯開山法燈円明国師之縁起』(1280年に原本が成立)によれば葛山景倫は、実朝の命にて宋に渡るべく鎮西博多津に下って宋船の順風を待っていたところ、実朝逝去の知らせを受けて出家したとあります。(以上、源 2019)。つまり吾妻鏡記述の時期よりも後、実朝暗殺の少し前くらいに実朝の命を受けて唐船による渡宋計画が実行されつつあったが、暗殺によって九州で頓挫したという伝承があるのです。それらを比較検討した結果、将軍あるいはその使者が唐船で南宋に渡ろうとしたこと、船は由比ヶ浜から出帆を果たしたということは史実だろうとする論文があります(大塚紀弘「唐船貿易の変質と鎌倉幕府」(『日宋貿易と仏教文化』吉川弘文館、2017年)
従来は「にわかに信じがたい」伝説という見方(山本幸司 2001)が多く、坂井氏も五味氏も特に史実としては取り上げてはいませんが、そのように、時期は違えど実朝が作らせた船が由比ヶ浜を出て九州あたりまで行ったという逸話が様々な伝説となっているのは確かです。
・考察
『右大臣実朝』『北条政子』などで、陳和卿は胡散臭い人物として描かれています。ドラマではそういう文芸作品の陳和卿像を引き継いだのかもしれません。ただ、それらの文芸作品では胡散臭さを実朝が理解して利用するくらいの勢いでしたが、ドラマでは素直に信じて騙されたような感じになっており、理性的で政治的な実朝像としては描かれませんでした。またそれらの作品では陳和卿自身が食い詰めたために鎌倉殿を次のカモにした的な描かれ方でしたが、今回は上皇の差金ということになっていたのもポイントです。
またドラマでは、宋船プロジェクトには結構色々な要素が詰め込まれていますが、全て充分描写されてはいなかったように思います。
①宋との貿易をする(陳和卿の言葉)
②実朝は聖徳太子が隋に対してしたように、実朝も宋に使者を派遣しようとしている(泰時の言葉)
③いずれ宋に実朝自身が渡って医王山に行き、お釈迦様の骨を頂いてくる、それを通して為政者として徳を高めたい(実朝の言葉)
という目的が語られ、その結果の効果として
④実朝の権威が高まる(義村、上皇の言葉)
という話があります。
②と③は実は宋船プロジェクトに関わる史料にあるものであり、①は最近の研究で可能性があると指摘されています。
しかしなぜか登場人物の間では、その後③④ばかりが話題にされ、宋との貿易や国交による利益がどうとかいう話は全く出てきません。清盛の描写で、宋との貿易で富を築いた様子が描かれるのに、不思議な感じです。そして③④が強調されるあまり、なんとなく、実朝だけのために宋船プロジェクトが進んでる印象なのです(だからこそ、泰時がそういう印象を御家人に持たれないように御家人の名前を船に記す案を出すわけですが)。八田殿が自分の普請仕事の総仕上げ的に関わっていますが、あくまでも八田殿個人の話です。御家人が不満を持つ御所の修復案件のように、宋船プロジェクトもまた、御家人たちに関わりない実朝個人の趣味的なこととしてあるという感じになってしまっており、せっかく出てきた幕府全体に関わる①②の話が活かされず、ちょっとどうかなと思いました。
また気になるのが、夢や宗教的なものの扱いがドラマ内で変化しており、ドラマ前半と違って実朝のケースは周囲が現代的な反応をしているのが気になりました。当時の人にとって夢は決して馬鹿にしたり疑ったりするようなものではなく、内心各人がどう思うにしろ、夢を真面目に取り扱い夢のお告げ通りに何か事業をなすことが当たり前であるという社会的な共通認識があったと思われます。それは吾妻鏡にも様々な人が夢に従って何かを成した話が多く書かれていることからも伺え、義時や政子も例外ではありません。
ドラマでも、最初の方で何回も出てきた頼朝の後白河院の夢は、コミカルに描かれはしたものの頼朝の中ではかなり真剣に受け止められるものでしたし、義経が御館の幻を見るシーンも厳粛なものでした。また梶原景時が神という概念を引き合いに出して頼朝や義経を見ている考え方も真面目に受け止められるべき描写でした。それが大姫の描写からだんだん怪しくなり、実朝に至っては完全に疑わしいものという扱いでした。それもちょっと一貫性がないなと感じました。
11) 義時との関係
・ドラマ
義時との関係は最初は良好で、義時も少年将軍を支える気持ちでしたが、徐々に隙間風が。
時政に実朝が拉致された事件の後、全てなかったことにして時政を赦してくれと実朝が頭を下げたあたりから不穏な感じになります。実朝が頭を下げても冷ややかに見つめたまま。
実朝が疱瘡の後、心機一転政に取り組もうとしても主体的に発言させず、自分が主体で政治を行おうとします。政は宿老が行い実朝にはただ見守っていただく、とたびたび政子に言い、宋船のことをきっかけとして上皇の言いなりなので政から退いてもらうとまで言います。
それに対して、政子は実朝を守ろうとし、京から将軍後継者を呼んで養子にし、実朝はそれを補佐する大御所になるプランを提示。義時は反対するも、親王が下向することになって反対もできなくなります。
そして実朝が御所を将来的に京に遷すと述べたために内心実朝を見限り、公暁の実朝暗殺計画を知りながらそれを阻止しようとする泰時を押しとどめて、実朝殺害を幇助するのでした。
・史料・研究との比較
義時と実朝の関係では、官位の件で大江広元を通じて諌めたり、宋船の件で反対したりと、対立している様子が従来注目されてきました。また従来の実朝のイメージは北条氏に実権を握られていて無気力だったというもので、その意味でも義時とは敵対的だったという見方が強かった模様です。拝賀式でその場を体調不良で離れたというのも、彼の陰謀を疑わせるものでした。戦前の教科書類や文芸作品などを見ても、それが通説であったことがわかりむす
しかし最近の研究では、常に完全に同調していた訳ではなく、親裁を始めた最初の方は軋轢もあったものの、特に治世後半、親王将軍を迎えると決まってからは歩調を合わせているという解釈の傾向にあります。
また拝賀式の件は、後でも述べますが吾妻鏡のように自分から言い出したのではなく、愚管抄に書かれていたように中門にとどまれと実朝に言われてくたというのが真相のようです。北条氏を顕彰する意図の強い吾妻鏡ではそれは書きにくかったという見方が示されています。義時黒幕説はかなり下火の見方です。
また吾妻鏡をよく見てみますと、義時はよく正月の鶴岡八幡宮や二所詣の旅に供奉しています。官位のことや宋船修造を諌めた逸話の後の時期の、建保五(1217年)年1月26日〜2月5日の二所詣にも義時が供奉していますし、宋船の進水式も義時が監督しています。その年、出家した大江広元の跡を継いで、陸奥守兼任に実朝から推挙されました。諌めたからと言って、関係が悪化してるようにも見えません。
そもそも実朝の少年時代からよく義時邸や義時の山荘に実朝が訪ねており、その最長のものとしては、建保三年(1215年)8月22日〜11月8日の75日間、地震や鷺の怪異を避けるために義時邸に移り住んだことが挙げられます。その間は義時は別のところに移り住んだようですが、義時は10月に桑糸五十疋を実朝に献上しています。
なお、ドラマでは御所を京に遷す計画を語って義時に見限るきっかけを作っていた実朝ですが、史料ではそのような動きは認められません。
・考察
ドラマは、吾妻鏡に見えるいくつかの軋轢を大きく捉え、後半になるに従ってその軋轢が大きくなるという、最近の史料から伺える方向とは逆のベクトルで描いていたと思います。諫言を何度かしていたのは吾妻鏡では確かなので、「いつも仲良し」ではなかったものの、治世後半になるに従って険悪に…とはならなかったと思われます。
義時はドラマでは「西の連中の言いなりにならない」ことを目指していて、そこが上皇寄りの実朝との確執の中心でした。義村なども「西の連中に乗っ取られるぞ」という懸念を示しており、そのような考えが坂東の御家人の一般的なメンタリティのように描かれています。ところが吾妻鏡などで見られる義時は、決してそのように朝廷に敵対的ではありませんでした。
当時、御家人である武士が、院や中央貴族など複数の主に仕えることは一般的であったといいます(岩田 2021)。そして承元三年の武芸を奨励するようにという諫言の内容も、よく読むと武芸に励み朝廷を護持することが鎌倉幕府繁栄の基礎であるということを述べており、軍機権門として朝廷を支える幕府像を説いているものでした。
また吾妻鏡には述べられていませんが、義時自身も官位が上がっており、実朝の官位上昇の恩恵に浴しています(岩田 2021)。吾妻鏡には時房が三位を願ったったことが書かれ、実朝から了承されています。実朝が朝廷に接近して認められ官位をあげることは義時をはじめとする北条氏の実利にもかなっていたわけです。そもそも頼朝死後にも引き続き三幡の入内を推進したのは政子や時政であろうこと、北条氏は家格上昇のために自分たちを王家の縁威に位置付けようとしたという見方も指摘されており(元木 2019)、北条氏が朝廷に接近し家格をあげることを忌避するとは考えにくいことです。
義時が実朝に実権を持たせず、武家の都を作ることを主張し、それを妨げる実朝を排除するというストーリーラインが本ドラマの中心としてありますが、そのような「朝廷と距離を置いた武家政権を作ることを主張する」「実朝を排除しようとする」義時像は、実は共に現在は否定されているかなり古い見方であります。実朝暗殺の黒幕は義時であるという説は古くからあり、明治時代の中学生向けの教育書籍にも既にそのような記述があります。明治大正に作られた歌舞伎でも義時が実朝暗殺の黒幕でしたし、永井路子の『つわものの賦』でも、北条黒幕説が通説のようになっていると語られています。安田元久氏の『人物叢書 北条義時』(吉川弘文館、1961年)でも、やはり義時が黒幕であるとしています。その上、同書ではかなり本ドラマに近い、武士階級の政権を強固にしたいという思想を持った人物として描かれているのも興味深いところです。義時の目的を武士社会独自の政権の発展、武士領主層の繁栄であるとし、その政策のために北条の独裁的体制を作り上げたとしています(安田 1961)。(ただし皇族将軍は自らの傀儡にするために義時が発案したとあります)
またドラマ義時は頼朝自身が武士の都を作ろうとして都から距離を置いたことを再三述べ、自分はそれを継承しているのだ的なことを言いますが、実はドラマでも頼朝についてそのような描写はありません。平家を倒すのも君側の奸を倒して後白河院を支え、あるべき世に戻すという趣旨のことを言っています。そして史実でもまた都への反発的なことはなく、むしろ頼朝は王朝の権威に依拠して主従関係を維持していたとの指摘があります(元木 2019)。東国武士伝統の父子関係の上下よりも王朝の権威である官位を重視し御家人の序列化を図りました。そして娘たちの入内工作を図り、天皇の外戚になることを望みました。
そのような意味でも、義時の「頼朝の御意志」で武家の都を作る的な考えはかなり不自然で、いったいどこから来たのか視聴者としては悩むところです。武家の世を作りそのてっぺんに北条が立つ、というのは、ドラマでは兄の宗時であったはずです。
12) 泰時との関係
・ドラマ
実朝が少年の頃から世話をし、彼から密かに想いを寄せられます。途中で世話役を交代し父の側で働きますが、優しく見守り励まします。ついに想いを歌にして渡されますが(1208〜1211)、和歌を作ったことのない泰時は悩みまくります。そこへ仲章がやってきて恋の歌だと告げ、やっと意味がわかります。しかし考えた挙句間違いではと言って返却し、別の歌を返されるのですが、それは恋が破れたさまを歌ったもので、泰時もさすがにその意味を悟るのでした。
その後しばらく接触はありませんでしたが、和田合戦で目の前で義盛を惨殺された時、慟哭する実朝を鶴岡八幡宮に避難させるという劇的な形で再会しました。
和田合戦を契機に親裁の決意を新たにした実朝から、義時に意見できる唯一の者として側近に取り立てられ、彼を補佐しながら共に政を行います。まだ若い二人は未熟ながらなんとか善政に努めようとしますが、義時に阻まれることが多く四苦八苦。しかしなんとか実朝を支えようと頑張ります。政子も実朝陣営に加わり、京から後継者を迎えて実朝自らは大御所となり権力を持つやり方にシフトしようとします。
泰時もその体制作りに協力する一方、実朝から讃岐守にも推挙されますが義時の思惑もあって固辞します。
実朝右大臣就任の拝賀の儀では警備を担当しますが、義村の援助で公暁が襲撃する可能性を察知して、実朝に束帯の下に武装することを強く勧めたり、義村を封じ込めるなど措置を次々と行います。しかし襲撃計画に父も入ってることを知って一旦父を探して階段そばから離れてしまい、そこで父たちに止められたために暗殺阻止ができませんでした。
実朝死後も、親王将軍を実朝の悲願として強く主張しました。
・史料・研究との比較
実朝の身辺の世話を泰時がしていたという記述はありませんが、早い時期から和歌会に出席していました。また1212年2月には政子と実朝の二所詣に時房らと共に付き従ったり、3月6日の御鞠始に時房、東重胤、和田朝盛、北条朝直らと共に祗候したりします。
泰時の名前がよく上がってくるようになるのは、和田合戦が起きた1213年あたりからです。この年は泰時大活躍でした。
1213年2月1日「梅花、万春を契る」の題の幕府和歌会に出席。翌日2月2日、実朝の側に仕える者の中で芸能に優れた者を選んで結番し、和漢の故事などを講じさせるという学問所番と称した制度が作られましたが、「一番」の筆頭に泰時が選ばれました。また和田合戦で活躍して褒美を取らせるという時に、義盛は主君に逆心を抱いたのではなく義時を恨んで謀叛を起こしたわけで、自分は父の敵を攻めただけであり、賞をいただくべきではないと答えて世間の人びとから感嘆されました(実朝は当然の恩賞であるから受けるようにと重ねて命じました)
7月7日の御所の和歌会に参加。8月26日、広元邸への御行初の供奉人として参加。9月は12日の千人もの参加者のあった駒御覧を進め、22日は秋の草花を見るための火取沢散策に歌道の心得ある者たちのひとりとして供奉。
1214年は1月22日鶴岡八幡宮参詣に供奉。3月9日、桜を観に急に永福寺に出かけた時に数名と共にお供しました。主従共に徒歩で行き、帰りは牛車を用意というあたり、ほんと急に思い立ったた感がありますね。7月には大慈寺の供養に供奉。
建保三年(1215)は元旦の八幡宮参拝の供奉くらいで、その翌年も特に目立った実朝との交流は見えません。(建保三年〜五年あたりは吾妻鏡自体の記述が少ない)
建保五年(1216) は3月の一切経会の使者を勤め、12月は25日に方違のために内々に永福寺に渡ったさい供奉し、その夜は一晩中続歌の御会が催されました。もしかしたら8月に開催された庚申の夜通しの和歌の御会にも参加していたかもしれません(参加者名は記録なし)
建保六年1月には泰時を讃岐守に推挙(三月に辞退)。7月22日、侍所司五人が定められ、泰時が別当に任命。9月13日、明月の夜ということで御所で開かれた和歌の会に参加(7〜8名)。
注目すべきは、将軍権力強化のための政所改革として政所別当を9人に増やした後、1218年に侍所別当に義時でなく泰時を据えているところです。義時から侍所別当の地位を譲られたとも考えられますが、吾妻鏡の記述では実朝が設定したことになっています。そして義時が侍所別当であった時にはあった北条氏の特権的なものが外され(北条氏の被官が所司から除れる)、また三浦義村らを指揮して御家人を奉行するようになります(『吾妻鏡の方法』)。
また、泰時は実朝から政治的に大きく影響を受けたとする指摘もあります(五味 2015)。吾妻鏡の書き方が、頼朝から正当な政道が実朝&泰時に受け継がれたという描き方をしているという研究もあり(藪本 2022)、実朝と泰時はともに良い政を行う名君という共通点があるという吾妻鏡の書き手の意識を感じさせられます。
・考察
泰時と実朝は、実朝の生前は史料ベースでは個人的なエピソードはそれほど多くはありません。
むしろ吾妻鏡を読むと、ドラマでは登場しなかった数名の御家人との、和歌を通じた親密な交流の逸話が印象的に語られています。たとえば「君ならで 誰にか見せむ わが宿の 軒端ににほふ 梅の初花(あなた以外の誰にみせようと思うだろうか、わが家の軒端に美しく咲いて香りを放つ梅の初花を)」という歌を贈った塩谷朝業の逸話や、和歌会の常連で寵愛深く「並びない近習」(建永三年11月18日条)と言われた東胤重が下総国に下向し、数ヶ月戻ってこなかったら勘気を被ったとか(義時に相談して和歌を献上したら機嫌が直った)、そして寵愛されること深く、同輩は誰も争わなかったという和田朝盛(義盛の甥)が和田合戦の近くに出家してしまい、一旦御所に呼び寄せたものの結局去られてしまったので「恋慕」が甚しかったとか。
しかしその一方で、よく読み込むと、和歌を通じた結びつきは泰時も結構強いことがわかってきます。吾妻鏡の中で、和歌会および、実朝が和歌の心得のある者と共に花鳥風月を愛でる外出をした条をピックアップして出席者を書き出してみたら、どの御家人よりも泰時が一番多く名前があがっていることがわかったのです。記載されている名前だけで考えると、もっともコンスタントにそのような会に出席していたことになりますね。北条氏の中では唯一の常連でもあります。また急に思い立って行く、あるいは内々に行く、というような時にいつも同行しているので、北条氏の中ではもっとも気のおけない仲だったのかなと想像してしまいます。目立った逸話がないけれども、地味に結びつきが強いというのは、なんともドラマの実朝と泰時らしい感じですね。(下の表は和歌会出席者を筆者が調べたもの)

また泰時が1218年に侍所別当に泰時が就任して御家人を統率しようとする姿は、まさに実朝が泰時を取り立てて自らの政を進めていた証であり、ドラマでの描写の理由の一つとなった可能性があります。
そして減税により撫民政策を共に推し進めようとする姿 は二人に共通しています。
13) 実朝暗殺までの公暁を中心とした動き
・ドラマ
公暁が京から戻りますが、自分が後継者だと思い込んでいたところが、実朝から直々に後継者は京から迎える、その相談相手になってほしいと告げられます。怒って京に帰ると義村に告げるも、千日参籠をしてる間に私が何とかしますと言われます。
その間に上皇から後継者について知らせが来たので、皆を集めて発表する実朝。そこに千日参籠を抜けて参加する公暁ですが、そこで親王がくだることを知らされ愕然とします。
しかし三浦が這い上がる最後のチャンスと思い、扇動する義村から父頼家の死の真相も告げられ、北条を憎むように。北条と実朝をうつことを決めます。
・史料・研究との比較
1217年6月20日、頼家の子公暁阿闍梨が園城寺から下ってきて、政子の命により鶴岡別当定暁の跡に入って別当になりました。10月11日に鶴岡別当になってはじめて神拝を行ったもののすぐに宿願により一千日にわたる宮寺参籠に入ってしまいます。それから一年あまり公暁の動静は『吾妻鏡』から消え、建保六年12月5日条に公暁は参籠したまま退出せず、ずっといくつかの祈請を続けていて髪を切ることもない、人びとはこれを怪しんだという記事がみえます。坂井氏は別当としての公的な職務を果たさぬまま参籠を始めたところからみて、鎌倉下向の当初から公暁が何らかの目的を持っていた可能性を指摘し、「おそらく参籠中、園城寺で修行を積んだ僧侶として、実朝を呪詛する祈請をくりかえしていたのであろう」としています(坂井 2014)。
また12月5日条によれば、公暁は白河左衛門尉義典を、伊勢大神宮をはじめとした諸社に奉幣の使節として派遣しましたが、義典は翌年二月、鎌倉への帰途、公暁の死を聞いて自殺してしまいます。坂井氏は、この義典は実朝暗殺の成功を祈願するための使節であったとも考えられ、建保六年10月、実朝の内大臣任官後のどこかで親王将軍擁立の情報に接し、追い詰められた、切羽詰まった精神状態のなかで呪詛から暗殺へと方針を転換したと考えられると指摘しています(坂井 2014)。
義村の公暁への教唆・協力という動きについては、作家永井路子氏の提唱以来かなり有力な説として流布しましたが、最近の研究では否定される傾向にあります(坂井 2014、山本みなみ 2022)。
・考察
公暁は千日参籠中抜け出したという記録はなく、有力御家人を集めた親王将軍発表の場にいたのは創作です。ただ、坂井氏が指摘するように、途中で諸社に奉幣の使節を派遣したということは、何らかの事情が発生したことを窺わせ、次期将軍が親王に決まったことを知った可能性はあります。ドラマではそれを劇的に表現し、かつその場のやりとりから公暁も実朝も頼家の死の真相を知らないということを示すためにその場を創作したと考えられます。その後二人が真相を知ることで、実朝暗殺のシーンへ向けて物語は大きく動き出すわけです。
また実朝が抜け出して公暁に会うということも記録になく、可能性としてもあまりないようですが、やはり対面して話し合い、暗殺の引き金を改めてはっきりと引かせてメリハリをつけるために創作されたようです。史実の公暁はずっと実朝に会わず色々計画を進めてたようですが、それですとインパクトに欠けると思ったのかもしれません。
またドラマでは、三浦がのしあがる最後の機会であるとして公暁を教唆して実朝暗殺に向かわせますが、これは上記のように現在では否定されている考えです。
14) 実朝暗殺
・ドラマ
数名の共謀者と共に大銀杏の影に潜んで拝賀式の帰りを待っていた公暁は、はじめに仲章を義時と思って殺します。仲章が叫びながら走り回りとどめを刺されて絶命すると、今度は実朝に向かいます。
ようやく階段の下に走り出てきた泰時が鎌倉殿!と叫ぶも、実朝は懐剣を手放して微かに頷き、自ら公暁の刃に倒れるのでした。
そこで公暁は、阿闍梨公暁、親の仇を取ったぞ!と叫び、源氏嫡流簒奪の企み、ここに…と用意した文書を読み上げようとしますが、実朝の遺体の上に取り落としてしまい、血が滲んで読めません。義時が討ち取れ、と叫ぶと兵士が一斉に襲いますがなんとか逃れます。御所に潜入して鎌倉殿の証の髑髏を手に入れ、政子に傷口を手当てしてもらったあとに義村邸にて食事をしますが、義村に殺害されます。
・史料・研究との比較
史料と言っても『吾妻鏡』『愚管抄』『六代勝事記』『承久記』等で結構記述の相違があります。
『愚管抄』に迫真の描写がありますが、慈円が実朝のもとに派遣していた弟子の忠快のみならず、公卿の坊門忠信、西園寺実氏、藤原国通、平光盛、藤原宗長らから聞き取ったものであり、その信憑性は高いとしています(五味 2015)。 坂井氏も関係者から聞き取って2年後に書かれた愚管抄が一番信頼性があるとしており、いずれにせよ愚管抄描写が一番現実に近いと思われます。
<愚管抄>
実朝が拝賀を終えて社殿前の石段を下りて、公卿が立ち並ぶ前を、下襲の裾を長く引きながら歩いていた時、法師の格好で頭に山伏の兜巾をかぶった男(公暁)が走りかかり、下襲の裾に乗ると、「ヲヤノ敵ハカクウツゾ」と叫びながら太刀で頭部に切りつけました。実朝が倒れると、男は即座に首を打ち落として取っていきます。
彼が「ヲヤノ敵〜」と言ったことは「公卿ドモアザヤカニ皆聞ケリ」と記しています。
続けて同じような格好の者が三、四人飛び出し、松明をかざしていた源仲章を北条義時と思いこんで斬り殺しましたが、義時は奉幣の前に実朝から「中門ニトヾマレ」と命じられ、御剣を捧げもったまま中門付近に控えていたため無事でした。現場にいた公卿などは「皆蛛ノ子ヲ散スガゴトクニ」逃げましたが、鳥居の外に控える随兵の武士たちは惨劇にまったく気づかなかったといいます。
公暁は幕府の長になろうと思うと義村に伝言して義村邸に逃げ込もうとしましたが、義村は追手を差し向け、塀を乗り越えて中に入ろうとしたところで討ち取られました。実朝の首はその後岡山の雪に中より発見されたといいます。
<吾妻鏡>
愚管抄と比べると、まず大きな違いは義時がどのように実朝の側を離れたかということです。
前の晩雪が二尺も降る大雪になりましたが、午後6時ごろ御所を実朝の行列が出発します。実朝が八幡宮の楼門を入るとき、義時はにわかに気分が悪くなり、捧げもっていた御剣を仲章に譲って退去し、神宮寺で正気に戻った後、小町大路にある自邸に帰ったといいます。つまり拝賀式の前に自分から体調不良で離脱していたとあります。
実朝殺害時の描写も微妙に異なります。拝賀の行列の名前の列挙の後、神拝を終えて退出してきた実朝を、石の階の際で窺っていた公暁が剣を取って実朝を殺害したとあります。ある人によれば、公暁は石段の上の鶴岡八幡宮本宮で、父の敵を討ったと名乗りを上げました。仲章殺害については触れられていません。その後随兵たちが馬で駆けつけたが、公暁の姿はすでになく、公暁は後見人の僧侶宅に逃れます。そこで実朝の首を離さず食事をとりつつ義村に幕府の長になることを伝えますが、義村は義時に公暁の件を伝え、殺害します。
<承久記>
儀式が終わって出るころ、何人かの薄衣を着た女房たちが、中の下馬先の渡り廊下から走るのが見え、そのものたちが石段のところで窺って実朝に襲い掛かります。一の太刀は笏で受け止めて、ニの太刀で切り伏せられます。
坂井氏は、吾妻鏡の記述する行列の順番に注目し、順番的に仲章に義時が具合が悪くなったから変わってくれと連絡するのは難しいとしています。実朝から中門にとどまれと義時が命じられたというシチュエーションも、北条氏には不名誉な事なので変更されたのだろうとしています。
ちなみに泰時が駆けつけようとして駆けつけられなかったことは史料には見られません。
また公暁が大銀杏に隠れていたということは江戸時代の文献初出で、それが鉄道唱歌になって一般化したと見られています。
https://web.archive.org/web/20190507003240id_/https://www.jstage.jst.go.jp/article/plmorphol1989/13/1/13_1_31/_pdf
13_31.pdf
・考察
ドラマでは、愚管抄の描写はもとより、吾妻鏡の描写でもない、かなりドラマチックな変更をおこなっています。
たとえば公暁の犯行は、突然後ろから襲いかかって裾を踏んで切りつけ、倒れたところを首を落とすという、あっという間の出来事だったようですが、それがドラマでは、皆が見守る中、階段の真ん中でじっと見つめ合ってからおもむろに殺すという、非常に演劇的なシーンになっていました。
公暁が大銀杏の影に隠れていた、という有名な逸話は後世の創作ですが、それも使っています。(44回で出てきた地図でわざわざ「大銀杏」のマークがあります)
公暁が「親の仇をうった」と叫んだのは、愚管抄準拠で史実に沿っていますが、そのあとに正当性を演説しようとしたのは創作です。また公暁は実朝の首を取って、それを離さず見方の僧侶の家でご飯食べたというエピソードが有名ですが、こちらの方は逆にドラマチックさを避けて首ではなく、鎌倉殿のレガリアたる髑髏に変更されています。最期は義村の家で義村本人に討たれる、という変更がなされています。
また義時が列を離れたタイミングおよび仲章交代自体は吾妻鏡準拠ですが、仲章は突如現れて強引に義時と入れ替わったことになっています。仲章は義時の放った刺客に襲われたものと義時が思い込んでいたが実は生きていた…という設定のためです。
そしてこれは大きなポイントですが、そのように偶然列を離れた義時は実朝暗殺計画を泰時から事前に知らされますが、泰時を止めて暗殺幇助的なことをします。これは昔ながらの「義時が黒幕かもしれない」という解釈の採用であり、最近の研究でわかってきた義時も実朝と協調路線だったこととは相反する描写です。
ちなみに天候ですが、その晩に大雪が降って二尺積もったという記述はありますが暗殺の時降っていたかどうかは定かではありません。明治時代にいくつか作られた、実朝暗殺をモチーフにしたらしき演劇や歌舞伎の錦絵を見ますと、雪が降ってたり降ってなかったりします。現代の学習漫画でも同じくです。
香朝樓: 「源実朝 中村福助」「禅師公暁 尾上菊五郎」 - Waseda University Theatre Museum - Ukiyo-e Search
そして先程も述べた、公暁と実朝がじっと見つめ合うシーン。公暁が飛び出してきた時はかなり驚愕した顔をしており、公暁の襲撃が全く予想外だったということが表れています。そこで対峙しますが、泰時からもらった懐剣を引き出して握りしめて、そろそろと抜きかける実朝。しかし儀式の前に邂逅した歩き巫女の「天命に逆らうな」という言葉を思い出して懐剣を取り落とし、微かに微笑んで頷き、公暁の刃を受けます。この「頷く」というのはト書にあったそうです。
これは明らかに明月記や吾妻鏡の記述と異なります。ではなぜそのようにしたのでしょうか。
まず、すぐに殺されない、多少は応戦しようとした、という作劇のヒントを与えたと思われるのが、『承久記』の記述です。承久記では笏で最初の太刀を受け止めるという記述がありましたが、ドラマでは笏ではなく懐剣で応戦しようとしかけた形に変えられていました。
そして「自ら公暁の刃を受けて死ぬ」という描写、これは「死を前もって覚悟していた実朝」という、昔ながらの実朝像の影響が大きいのではないでしょうか。確かに、将軍になって以来北条氏に実権を握られて厭世的になり、宋に行こうともしていた…とか、自分もいずれ北条氏に殺されるのではとかいう形での「死の予感」をしていたという従来の描かれ方とはドラマは違う描き方をしており、その意味で以前から死を意識していたようには見えませんでした。しかし頼家の死を知るタイミングを拝賀式直前にし、それによる自らの地位への疑い、公暁への済まなさ、公暁が自分を憎み殺そうとする気持ちへの理解が発生したため、公暁を前にして「死を受け入れる」実朝になったと思われます。
もっとも一旦は公暁の説得に成功したと思っていた訳で、だから彼の登場に驚いた顔をしていました。しかし、懐剣を取り落とし頷く姿からは、ああ、やはり私の説得如きでは無理だったのだなあ、それは仕方のないことだ、と感じたような印象を受けました。
ただそうなると、「出ていなば」の辞世の句を一体いつ詠んだのか?という疑問が生まれます。公暁の登場に驚いていましたが、心の底では殺されるかもしれないと感じていたのでしょうか。「太郎のわがまま」を所持していたのも、少しは襲撃を予想していたのでしょうか。
ちなみに柿澤氏のインタビューでは、公暁に会いにいく際に実朝が感じていたこととして
>「謝るしかないし、殺されることも覚悟していた。」
>「詳しくは言えないんですけど、あそこに行く前に、実朝はあることをしていると思う」
と語っており、演じ手の解釈としてはもしかしたら辞世の句はこの時書いたという設定にしたのかもしれません。
「鎌倉殿の13人」寛一郎と柿澤勇人が語る公暁と実朝、対話の舞台裏 寛一郎「公暁には『許す、許さない』の葛藤があった」(エンタメOVO) - Yahoo!ニュース
15) 実朝の「京志向」「武を軽んじる」について
・ドラマ
ドラマの実朝は、あまり京への執着・関心を示していません。
確かに京の上皇を政の手本としようとしますが、あくまでも自分の名付け親の上皇の政治手腕を尊敬してということからです。和歌を愛し定家から添削も受けますが、それによって京に憧れるという描写はありません。しかし44話で唐突に、将来的に御所を京都に遷すという計画を述べています。
武芸に関しては、確かに少年の頃課せられたスパルタカリキュラムを受けている様子では、どうも武芸系は苦手なのだなとわかりますが、それでその後非難されてはいません(義盛に武家の棟梁なんだからそんな細い体では…とはっぱをかけられる程度です。切的では楽しく弓の競技を見物しており、そういうものに興味がないという描写はありません。
・史料・研究との比較
実朝の京への憧憬の証としてよく引き合いに出される京かから御台所を迎える件は、上でも書いたように周囲の大人の思惑が強いものでした。京文化である和歌への傾倒も、やはり上記のように政子のお膳立ての可能性が指摘されており、また和歌は政と直結するもので、為政者として当然の嗜みでした。周囲に「京に馴るるの輩」を置いていたとの記述もありますが、それは政の必要に迫られてのものとも言えます。
実朝はむしろ京にのぼりたいと願い出た御家人を叱責したこともあります。
蔵人左衛門尉時広が禁裏奉公のため上洛することを申し出たため、実朝の気色は頗る不快で、殿上の仙藉に交わってからの下向であるのだから、京に帰る必要はないであろう、帰りたいのは関東を蔑ろにするつもりなのか、と叱咤したといいます。これに時広は、京都を中心に考えているのではなく、御拝賀の前駆のために駆けつけた故、まだ十分に朝廷に仕えておらず、幸いに除籍されてはいないので、まげて恩許を蒙って望みを達したい、と義時に泣いて訴え、やっと実朝から上洛を認められたとのことです。
とはいえ、確かに京風文化を積極的に取り入れる傾向があったのは確かです。たとえば和田合戦で消失した御所の再建の際に、実朝の指図で中門を建てることとなりましたが、これは京の寝殿造の御所と同じく中門廊を構えることにしたもので、京文化が御所の建築にまで及ぶようになった証です。また新御所の障子の絵図の風情が実朝の意にはかなわなかったことから、職者に尋ねるよう京の佐々木広綱のもとに伝えています。左大将拝賀の儀の際には、後鳥羽から下賜された檳榔毛の牛車や、豪華な調度・装束が人びとの眼を驚かせました。
和歌の名手ということが有名ですが、実は蹴鞠にも興味を示しています。元久二年(1205年)三月一日に若宮別当坊で蹴鞠を遊ぶなどしでおり、 21歳の建暦二年(1212年)になると、実朝はみずから「旬の御鞠」を発案し、メンバーを厳選して「幕府御鞠始」をおこなうようになりました。
武芸に関しては、諫言を受けたり暴言吐かれたりする逸話が有名ですが、しかし吾妻鏡を見ると相撲や流鏑馬などの武芸を見るのは好きそうな感じで、現代でいうところの見る専だったような印象を受けます。
・考察
従来実朝を描いたものでたいてい触れられていた実朝の「京かぶれ」について、本ドラマでは全く触れていないのは大変画期的であると思いました。ドラマのみ見て従来の実朝像を知らない人は、まさか実朝が京かぶれ的に批判的に言われていたとは全くわからないでしょう。また武芸を怠ってるという非難をされていたともわからないはずです。武芸が不得意でも見るのは楽しいという描写は、吾妻鏡に沿ったものでした。
その意味で、過去の実朝像は相当払拭されたと言っていいでしょう。
ただ、上皇の政のやり方に学び親裁を行おうとし、それだけならまだしも知らず知らずのうちに宋船の件で上皇の差金にのり、「自身を揺るぎない鎌倉のあるじ」とするため、上皇の子供を後継とし自身は大御所となる構想を立てる…と、全て上皇の思うままというか上皇の操り人形のような描写になってしまい、さながら「上皇かぶれ」というべき状態の描写になっていました。
京志向/武芸蔑ろ的な吾妻鏡の逸話が全てばっさり削除されてたのは大変思い切った描写でしたが、その代わりに別の側面で京からの悪しき影響を受けている描写になってしまっています。
16) 官位について
・ドラマ
ドラマでは43、44話で実朝の官位昇進が述べられます。
親王将軍の後見として左大将に昇進し、頼朝の右大将を超えたと仲章に言われます。微妙な表情をしながらもおめでとうございますと言う義時、そして泰時。実朝は従三位に尼御台が叙されたことも告げ、そうなるとできれば太郎にも官位を…と望み、仲章に相談して讃岐守に推挙しようとします。しかし仲章に借りを作りたくない義時は反対します。
またその後、将軍になるのが頼仁親王と決まったあと、一日も早く鎌倉殿を親王にお譲りし、父上も見たことのない景色を見たいと言います。つまりそれは大御所になり、さらに強大な権威を手に入れるということでしょう。
右大臣昇進自体は直接描かれませんが、それに喜ぶ北条一族は描かれます。浮かれる人々を見て呆れる義時に、身内から右大臣が出たのが嬉しいんですよと語る政子。
左大将、右大臣昇進を含め、実朝の官位上昇については特に何も言わず、各種儀式を滞りなく進めたい義時ですが、将来的御所を京に遷すという構想を実朝に告げられた途端、強く反発し、見捨てる決心をします。あのお方は鎌倉を捨て、武家の都を別の所に移そうと考えておられる、そんなお人に鎌倉殿を続けさせるわけにはいかんと時房に告げるのでした。
・史料・研究との比較
一般的には実朝の朝廷趣味の反映、あるいは実権のない無力さを慰めるため分不相応に官位を欲していたように思われていた実朝の官位の上昇ですが、近年はそのような見方が否定される傾向にあります。
まず実朝の官位を整理しますと、1203年兄の跡を継いだ実朝は12歳で従五位下でスタート、2年後には五位中将、4年後18歳にして従三位になり公卿に。その後しばらく官職の動きはありませんが(位階は22歳で正二位になっている)、建保四年に25歳で権中納言になって以来急激に官位を上昇させ、右大臣にまで上り詰めました。
そのような急激な官位上昇について、承久の乱が起きた十数年後に原形が成立した『承久記』には、後鳥羽が実朝を「官打ち」にしたという記述がみられます。「官打ち」とは身にすぎた高い官職を与えて災いが及ぶようにする一種の呪詛であり、この官打ち説に対しては長らく額面通りに受け止められる傾向にありました。
もっとも実は戦前から、これについて疑う意見が多少は出ていました(高須、1932・n三浦、1922・ 川田、1941 など)。しかし戦後も引き続き、学術的一般書においてすら官打ち説を肯定的に引用する記述が続きました(上横手、1958 など)。
他の貴族の官位上昇と詳しく比較検討して、官打ち説を否定したものとして有名なのが、1997年の元木泰雄氏の論文です(「五位中将考」(大 山喬平教授退官記念会編『日本国家の史的特質 古代・中世』思文閣出 版、1997年)。本論文では、官打説の当否について上皇と実朝の関係を深く分析することについて「本稿ではこの点に立ち入ることを避け」るとしているものの、実朝の家格と昇進の関係を考えると「晩年の実朝の昇進は決して異常と言える程のものではなく、元来摂関家庶子なみに位置付けられた家格から考えると、彼の昇進を『官打ち』とする説にはにわかに従い難い」としています(同書p. 502-503)。詳しく見ますと、実朝は「官職」の面では、公卿昇進の年齢は摂関家庶子なみであったり、権中納言昇進年齢は、他の同職に昇進した公卿たちより年齢が遅かったりするなどのスピード感でしたが、「位階」の面では22歳で正二位になるという摂関家嫡流並みの扱いで、彼の家格を反映してると指摘します。また実朝は五位中将を経験し権中納言中将という地位につきましたが、そのような昇進をした者の多くは摂関家嫡男でありました。建保六年に左大将昇進に固執したのも、左大将が摂関家嫡流が多く就任した官職であったことと関係している可能性も指摘しています。
それに基づき、岩田慎平氏は実朝はその家格から、彼自身の意志はともかく以前からその昇進ルートは敷かれていて、実朝はそれを大過なく辿っているに過ぎないと指摘します(岩田、2021)。兄頼家は五位中将の地位を認められ、実朝も五位中将を経て中納言中将の地位を得ますが、通例はこのあと大将をへて大臣に就任するわけで、実朝もそのルートに乗ったということになります。野口氏も摂関家に準ずる権威を付与されていたことからすると決して異常というほどのものではなく、後鳥羽院と実朝の蜜月の証と捉えるべきであるとしています(野口、2022)。
もっともそれに対し坂井氏は、官打ち説を後世のこじつけにすぎないとしりぞけるものの、昇進自体については、上皇が「親王を補佐するのにふさわしくなるよう、異例の速さで実朝の官職を上昇させ、年末には右大臣という信じ難い高官に補任した」(坂井、2022)と述べており、かなり異常事態と捉えています。しかしその異例さというのは、「(前任の)良輔の死去という事情があったとはいえ、内大臣任官から二ヵ月も経たないまさに異例中の異例という速さである。太政大臣が名誉職化していた当時の官制体系にあって、右大臣は左大臣に次ぐ、武家ではとうてい到達することのできない想像を絶する高い地位であった」(坂井、2020)とあるように、あくまでも「武家としては」ということに着目した場合に、異例さが際立つという表現です。
いずれの立場にしろ、そのような高い官位を所望するのも、親王将軍の後見ということを見据えたものであり、よく言われていたような実朝個人の憂さ晴らしや名誉心からではないし、まして上皇の官打ちではないという見方が主流です。
そして有名な建保四年の広元・義時の官位を望みすぎることへの諷諫にしても、そのまま受け取るにしてはあまりにも不自然であることが様々に指摘されています。吾妻鏡によれば、建保四年九月十八日、義時は広元を招き、実朝が大将への昇任を内々に思い立った件について、壮年に達してないのにそのような官職の昇進ははなはだ急であること、また、御家人たちも京都に祗候することなく地位が高く重要な官職に補任されていている件も良くないと思っていることを告げ、広元から申し上げてほしいと依頼したというのです。広元はこ現在の官職を辞し、征夷大将軍として年齢を重ねてから大将を兼任するべきではないか、と諫言しましたが、これに対し実朝は、諷諫に感心するが源氏の正統は自分で絶えるため家名をあげたいと答えたことも有名です。
五味氏は、時期的に建保四年九月頃の記事としてはいささかおかしいという指摘をしています。その頃は実朝は権中納言中将になったばかりで直衣始もまだ行っていない段階だからです。関連記事がなく説話的な内容であることもあり、もしも仮にそのような諷諫があっても宋船が浮かばなくなった事件の後の建保五年九月頃だろうとしています(五味、2016)。
坂井氏はさらに詳しく述べており、この逸話が相当作為に満ちていることを指摘しています(坂井、2019、2020)。たとえば広元の「摂関の御息子にあらずんば」という発言は、頼朝頼家の代から鎌倉殿が摂関家とほぼ同格ぼ扱いを受けていたことを知ってる広元のものとして不自然であり、「中流貴族レベルの一介の御家人に過ぎない広元が、摂関家と同格である主君の将軍に対し、治天の君後鳥羽が任じた官職を辞任するよう勧めることなど、少なくとも承久の乱以前の朝幕関係の中ではあり得ない」(坂井、2020)と述べます。これは続く「いかでか嬰害・積殃の両篇を遁れ給はんや」、つまり災いから逃れられないという言葉を導き出すためのもので、実朝横死を因果応報的に正当化した吾妻鏡編纂者の作為ではないかというのです。それに対する、実朝の源氏の正統は自分で終わるという言葉も、同様に正当化のための作為ではとしています。さらには吾妻鏡では義時自身の官位上昇に関して口をつぐんでいながら、義時に御家人が高い官位につくことを過分であると非難させることも不自然であると指摘します。『鎌倉年代記』や『尊卑分脈』で見ると、この頃の幕府首脳御家人は揃って高い官位や地位を得ており、義時自身、建保5年に、まさに吾妻鏡で彼が非難した、御家人がおいそれとなるのを控えるべき、本来なら在京すべき顕要な職のひとつである右京権大夫に昇任しているのです。この諷諫に作為性があることについては、吾妻鏡の叙述について研究している藪本氏も同意しています(藪本、2022)
確かに建保六年には、実朝が官位上昇を望むと見られる記述があります。建保六年政子が親王下向の交渉のため鎌倉を発ったのが二月四日ですが、その六日後の二月十日には大将昇任という実朝の希望を朝廷に伝えるため大江広元が使者を京都に派遣、さらに二日後には、右大将ではなく必ずそれより上位の左大将にという実朝の意思を伝える使節が上洛しました。政子が京で交渉中に、朝廷に対し矢継ぎ早に使者を派遣して官位に対する要望を伝えているわけです。これを坂井氏は「実朝がその後見になるには、権大納言・右近衛大将を生涯最高の官職、いわゆる極官とする亡父頼朝より高い官職が必要だという実朝の意思表示だった」と見ています(坂井、2014)。五味氏は、その前年に発生していた朝廷の右大将人事の関係(後述)で右大将ではなく左大将を希望したのではとしています(五味、2015)。いずれにしろ重要なこととして、それは実朝ひとりの考えではなく幕府首脳の総意であろうということです。左大将人事の件は政子、時房、広元らが関係しており、実朝個人の趣味や慰めでも、まして自分で源氏が終わるので家名だけでも高めたいという気持ちからでもなく、幕府が一体となって進めた施策であったことが伺えるわけです。
・考察
実朝の急激な官位の昇進について、ドラマで
・ありがたく喜ばしいことであるが、特に異常なこととして描かない
・近年の研究で不自然さが色々指摘されている、官位上昇を諌める逸話がばっさりなくなっていた
となっており、研究成果を踏まえた大きな進展だと思います。坂井氏は官位については異常な昇進であるとしていますが、個人的には、元木氏が実朝と雁行して右大臣に昇進していると指摘している摂家嫡男の近衞家通の昇進と比べてもさほど異常には見えないところから、摂関家に準ずる家格の側面を重視し、先例を無視しがちな後鳥羽上皇の人事の傾向を考えるなら、当時の源氏の棟梁としてはそこまで異常ではないとする見方が妥当かと思います(筆者作成の下図参照)

また、特に官位に関する諷諫は昔からずっと実朝の逸話として代表的な話とされているものであり、「公家かぶれで孤立した悲劇の将軍、という実朝像の論拠になった記事」(坂井、2019)でした。これを描かないのは大英断と言えます。また左大将への昇進を実朝の官位上昇志向のためでなく「親王将軍の後見」のためと位置づけているのも、近年の研究動向に見合ったものでした。
むしろ、ドラマでは意識的に、実朝の朝廷に対する官位に関する働きかけを描かないようにしており「官位を欲しがる実朝像」にならないよう周到に描写しています。たとえば左大将昇進については、ドラマでは特に幕府からの働きかけはなかった描写ですが、実は上に書いたように実朝(と幕府首脳陣)が指定し要求した官職でした。そのような経緯を描かないことで、実朝の「官位を望みすぎる」「公家かぶれ」イメージを出さなないようにしてるわけです。
またドラマ内で実朝に敵対的に描写されていた義時すらも、一貫して実朝の官位上昇自体には特に不満は抱いていないように描かれていました。身内から右大臣が出ることを北条一族が喜んだ時もはしゃぎぶりに呆れつつも同調していましたし、官位関係で不満をあらわにするのは、泰時の讃岐守推薦に仲章がいっちょがみして恩を売ることに対してです。広元に至っては全くそれを気にする様子もありません。
そのように、自らの慰めのために官位の上昇をしきりに望む、という実朝像にしないということは、和歌や蹴鞠などの貴族趣味に耽溺して政を顧みない、あるいは北条氏に実権を握られてその慰めをそれらの文化活動に見出している、というステレオタイプの実朝像にしないことと共に「従来の実朝像の否定」であると思われます。和歌・官位へのこだわりは、従来実朝の極めて私的な志向として捉えられ、東国武士から浮き上がる要因とされていたものですが、近年の研究により、私的なものでなく公的なものとして、またそれらに積極的に関わることは東国武士の文化に反するものではないと捉えられるようになりました。
(もっとも、義時の諷諫のニュアンスは、ドラマで全く棄却されているわけではありません。若くして高い官位を得ること自体への反対は、泰時の讃岐守推挙への若輩者であるという反対意見に、頼朝と比べて実朝が実績がないとする気持ちは、官位で頼朝を超えたという仲章の言葉への苛立たしげな表情に、それぞれスライドさせて表現していると言えます。)
しかしその一方で、建保五〜六年の実朝の朝廷への官位絡みの働きかけで、実朝のみならず、幕府首脳の官位・地位が上昇したことを描かなかったことで、次々と朝廷に要求を認めさせていった実朝の影響力が描かれなかったのは残念なことです。上にも少し書きましたが、左大将の件は実朝側が強く要求したのですが、実はその前年にも、右大将の人事をめぐっても実朝の意向が大きく影響する事件が起きました。愚管抄によれば、建保五年に、幕府と朝廷の取次役である西園寺公経が上皇の右大将人事に不満を持ち、遠縁の実朝にその件を訴えると言ったと上皇に伝えられたために上皇の勘気を被り、籠居という事態が発生しました。その際、公経のライバルの関係者である卿二位について、実朝が「敵に思う」とまで言って激怒したことが伝わったため、卿二位が驚き実朝をはばかって善処し、籠居は解かれたのです。これはドラマで全く描かれませんでした。この事件は従来一般にはあまり重視されなかったもので、取り上げられるとしても、その騒動の結果、上皇と実朝の間に軋轢が生まれたのでは…という解釈の中に嵌め込まれてきました。近年では、実朝の怒り→卿二位の驚きと対処→という動きの中で、卿二位が政子の従三位への働きかけをしたのではないかという、つまり実朝の怒りが結果的に幕府に有利な流れに繋がったのではということが指摘されるようになっています(田端、2005 五味、2015 野口、2022)。これまで実朝の事績としてこの件があまり取り上げられなかったのは、おそらく実朝が朝廷に強気に出るということが、上皇に従順だったり政治に関心がないという既存の実朝像にそぐわなかったためでしょう。
ドラマでもこの件が描かれなかったのは、朝廷の顔色を伺ってばかり・操られてばかりというドラマ内の実朝像と整合性が取れないためと思われます(煩雑さを避けるためももちろんあると思いますが)。左大将絡みで幕府首脳が一体となって朝廷に要求する動きをしたことを描かななかったのも、同様の意図からでしょう。「官位を望む従来の実朝像」を否定してはいるものの、実朝の対朝廷への影響力の大きさや幕府首脳陣との協調などの様々な新しい知見は、ドラマの流れと矛盾するために描写されなかったわけです。
ちなみに西園寺公経は実朝の遠縁(頼朝の姉妹・坊門姫とその夫一条能保の間にできた全子を妻)にあたり、上流貴族としてはそれほど家柄は高くなかったものの、幕府と朝廷の取次役として幕府にとって重要な人物でした。彼が養育していた孫が三寅な訳で、ドラマ内で三寅の血縁関係が義時らに飲み込みにくいという表現がなされていたのはいささか実際と異なるように思われます。
4.まとめ〜新しい実朝像になっていたか
全体に、新しい知見を取り入れたり細やかに史料を拾っているのは大変素晴らしい点と言えます。たとえば、実朝についてはどの時代のどの媒体でも言われがちだった「京文化かぶれ」「実権がないのを紛らすため和歌に耽溺・いたずらに官位を望む」が一切描かれませんでした。特に戦後史学や学習漫画等で強調されがちだった「東国武士から理解されず浮く・苦言を言われる」という描写もありません。和歌ひとつとっても、ネガティブな現実逃避の場ではない事、実朝が興味を持つよう和歌を政子が用意したり、その中でも頼朝の歌を実朝が好きになったりなど、研究や史料を細かく拾い上げています。
また政治への積極性を描き、義時に対抗していこうとする動きを描いたのも新しい点でした。多くの文芸作品などでは和田合戦を契機にやる気をなくしたとか死を意識したとなっていますが、ドラマでは逆に、最近の研究動向で明らかになってきた和田合戦以降将軍親裁を強化する動きを反映しているといえます。義時と対立的であるという描写は古いものですが、そこに接続された政治意欲の向上の描き方は新しいと言えましょう。
ただその一方で、その「義時と実朝が対立的である」という古い図式を温存したため、そして義時側を「是」とする作劇のために、実朝が「是」ではない側に立たされるということになってしまいました。
そしてその対立の原因が、朝廷を敵視する義時に対して朝廷を重視する実朝という事になっているのが、史料や研究から大きく外れてるところでした。義時の朝廷敵視が新しい研究ではそうではないということがわかってきています。
また、義時と実朝の対立のクライマックスになり、2人が完全に決別する最高潮になるべきシーンが、幕府を都に遷すという前触れのない実朝の発案シーンの創出で、ドラマ的に唐突感が拭えませんでした歴史的にも研究者からもありえないという意見が出ています。確かに「新しい」見方ですが、考えようによっては究極の「京かぶれ」(今まで封印してた)描写であって、古い実朝像から起因してるともいえましょう。
脚本家は、本ドラマの中で新しい説を取り入れながらも、通説も適宜取り入れて大切にするといったことを多くやってきました(「鵯越」など)。実朝像も、同じ手法を取り入れて、通説に馴染みがある人も親しめるように作った、と言えるかもしれません。しかしそのように、新しい知見と古い知見の接木は残念ながらぎこちないものになってしまいました。またせっかくかなり積極的に新説を取り入れた成果が、それにより霞んでしまった…という結果になってしまったように思います。
その理由として、史学上の「新しい実朝像」は「従来の実朝像」と真逆といっていいほどの評価であることがあります。特に戦後史学の中でかなり否定的だったのがかなり高評価になりました。つまり新しい像は古い像の付け足しや微調整ではなく、全く逆の価値観を示すものであったのです。水と油のようなそれらを混ぜるてドラマを作るのは、かなりな困難があったかと思われます。
そしてその像の変化の背景には、ダイナミックな中世史学の潮流の変化がありました。従来の実朝像の形成に重要な役割を果たしていた「従来の武士/公家像」の刷新、それに理論的背景を与えていたマルクス主義史観、東国国家論が後退・相対化されたことと、実朝の見直しは不可分であります。
このドラマにおける武士/公家像、中世世界の枠組みが、まさにその、現代では後退した「従来の史観」で描かれる旧態然としたものであること、義時が東国国家論を深く内面化した人物であり、京都とは隔絶した武家の都を作ると意志しており、そのような義時の思想を是とする描き方であることから、実朝は戦後史観の中でのように、義時と対立する存在に位置付けられ、その評価は必然的に低いものにされざるを得ませんでした。すなわち、あらあらしくも清新な武士が堕落した朝廷から独立し打ち破ることが「是」であり、そのような悪しき朝廷に接近したり取り込まれたりする実朝は未熟であり排除されるのもやむなしというものです。ですから実朝が良い政治をしたという吾妻鏡の描写も、無視されたり悪い政治だったという風に変更されました。それを基調とし、物語のアウトラインとしてるが故に、通説のネガティブさを省いたり政治に意欲を示すという「新しい実朝像」を打ち出してもそれらが旧説のネガティブな要素を打ち消しきれていませせんでした。
また一方で、従来の実朝像の踏襲として、死を予感し死を受け入れる悲劇の若き貴公子という、文芸作品で強調されてきた従来の実朝像がありますが、これはドラマ内での実朝評価を多少なりとも上げる結果になりました。主人公義時と逆の価値観を持ち、視聴者にも消されてもやむなしと思われてもいたしかたない実朝の死を、そのような悲劇性、崇高性によって彩り、視聴者が悲しく惜しいものとして受け止めるように作られていましたためです。これは、ドラマ内で否定的に描かれていた登場人物が、死に際に視聴者の同情や感情移入を一気に高めるように描かれるという、本ドラマの法則というべき作劇手法にも則っています。もっとも、その「死を予感する」内容を、戦前の教科書類や一部文芸書などで描かれていた、頼家のように北条氏から排除されるかもしれない、ではなく、恨みから公暁に殺されるかもしれないとしたことは、大きな変更でした。また頼家の死を知り公暁の恨みを知るタイミングを拝賀式直前にしたことは、ドラマ上の仕込みが足りなく唐突かつ不自然に見えました。その方向で描きたければ、もっと早くから色々と伏線が仕込まれていればと思えてなりません。
高橋昌明は『武士の日本史』(岩波書店、2018年)の中で、「儀式や享楽に明け暮れ、無為と退廃のなかで未来を見失った都の貴族を、地方で農業経営や開発にいそしみながら、たくましく成長してきた新興勢力の武士が圧倒し、やがて貴族に代わって、鎌倉時代という新しい武家の世を開いたとする見方」は、中世史の学界では今では過去のものになったにも関わらず、「一般にはなおこの理解が日本人の常識であり、ほとんどあらゆる歴史小説、テレビドラマなどの当然の基調になっている」(p. 11)と指摘しています。また、『論点 日本史学』(ミネルヴァ書房、2022年)では、戦前からある「文弱な女々しい貴族と健全で勇ましく男らしい地方武士という図式」と整合性のある「地方の武士が都市に巣食う古代貴族を倒して新時代を開いてゆく」という日本中世史理解、すなわち在地領主制論が戦後唱えられ、階級闘争史観に基づくこのような武士理解が今日に至るまで続く通説的理解を形成した、と述べられています(31武士論 p. 70)。そのように史学者側からは、古い武士観がいまだに強固に通説として流通し、エンタメなどで繰り返し描かれていることを指摘する声が様々にあがっています。今回のドラマの実朝像も、残念ながらその武士像に基づいた作劇によって描かれていますが、それだけに、昔から連綿として続くそのような武士像のレガシーから逃れるのは、エンタメ作者にとっては並大抵でなく大変なのだろうなあと実感しました。本ドラマで新しい実朝像もいくつか提示してくれたことを喜びつつ、もし今後さらにドラマなどで取り上げられる際には、刷新された武士/公家像も踏まえてくれたらさらにいいなあと思う次第です。
<了>
参考文献一覧(研究書系)
・石井進著作刊行会編『石井進の世界① 鎌倉幕府』(山川出版社、2005年)
・岩城卓二・上島享・河西秀哉他編著『論点 日本史学』(ミネルヴァ書房、2022年)
・岩田慎平『北条義時-鎌倉殿を補佐した二代目執権 (中公新書 2678)』(中央公論新社、2021年)
・上杉和彦『源頼朝と鎌倉幕府』(吉川弘文館、2022年)
・奥富敬之『鎌倉北条氏の基礎的研究』(吉川弘文館、1980年)
・上横手雅敬『人物叢書 北条泰時』(吉川弘文館、1958年)
・川田順『評釈日本歌集』(朝日新聞社、1941 年)
・黒田俊雄『黒田俊雄著作集5 中世荘園制論』(法蔵館、1995年)
・五味文彦、本郷和人(編)『現代語訳吾妻鏡〈7〉頼家と実朝』(吉川弘文館、2009年)
・五味文彦、本郷和人(編)『現代語訳吾妻鏡〈8〉承久の乱』(吉川弘文館、2010年)
・五味文彦、本郷和人(編)『現代語訳吾妻鏡 別巻 鎌倉時代を探る』(吉川弘文館、2016年)
・五味文彦『源実朝 歌と身体からの歴史学』(KADOKAWA、2015年)
・五味文彦『吾妻鏡の方法 事実と神話にみる中世』(吉川弘文館、2018年)
・坂井孝一『源実朝 東国の王権を夢見た将軍』(講談社、2014年)
・坂井孝一『承久の乱-真の「武者の世」を告げる大乱 (中公新書)』(中央公論新社、2018年)
・坂井孝一『源氏将軍断絶 なぜ頼朝の血は三代で途絶えたか 』(PHP研究所、2020年)
・坂井孝一『考証 鎌倉殿をめぐる人びとNHK出版新書 679』(NHK出版、2022年)
・関幸彦『戦後 武士団研究史』(教育評論社、2023年)
・高須梅渓『国民の日本史; 第五編 鎌倉時代 後編』(早稲田大学出版部、1923年)
・高橋昌明『武士の日本史』(岩波書店、2018年)
・田端泰子『乳母の力―歴史を支えた女たち (歴史文化ライブラリー)』(吉川弘文館、2005年
・永原慶二『20世紀 日本の歴史学』(吉川弘文館、2003年)
・野口実・長村祥知・坂口太郎『公武政権の競合と協調 (3) (京都の中世史 3)』(吉川弘文館、2022年)
・三浦周行『日本史の研究』(岩波書店、1922年
・三木麻子『コレクション日本歌人選 051 源実朝』(笠間書院、2012年)
・元木泰雄「五位中将考」(大 山喬平教授退官記念会編『日本国家の史的特質 古代・中世』思文閣出 版、1997年)
・元木泰雄『源頼朝 武家政治の創始者』中央公論新社、2019年)
・安田久元『人物叢書 北条義時』(吉川弘文館、1961年)
・藪本勝治『日本史研究叢刊44 『吾妻鏡』の合戦叙述と〈歴史〉構築』(和泉書院、2022年)
・山本みなみ『史伝 北条義時: 武家政権を確立した権力者の実像』(小学館、2021年)
・山本みなみ『史伝 北条政子: 鎌倉幕府を導いた尼将軍 (NHK出版新書 673)』(NHK出版、2022)
・山本幸司『日本の歴史09 頼朝の天下草創』(講談社、2001年)
・渡辺泰明編著『源実朝―虚実を越えて (アジア遊学 241)』(勉強出版,、2019年) (菊池紳一、坂井孝一、高橋典幸、山家浩樹、渡部泰明、久保田淳、前田雅之、中川博夫、小川剛生、源健一郎、小林直樹、中村翼、日置貴之、松澤俊二 著)